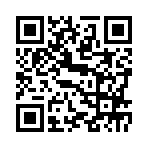2015年02月21日
晩秋のシーズナルパターン (その12) 第III期【水温4℃前後】ミノーの場合
晩秋の支笏湖に毎週通い込むと、ある日突然、シャローの湖水の淡い白濁と濃い緑色が消え、透明度が一気に上昇します。6回前の書き込みの写真をもう1回載せます。

湖水の透明度が一気に上昇したと同時に、水温が4℃前後に落ち着きます。これが、ターンオーバーが完了したことを示すサインです。例年、11月下旬から12月上旬の間のどこかで、これが突然起きます。第III期の始まりです。

私がこの4〜5年間に経験した限りでは、第III期には明確な特徴が2つあります。第一の特徴は「ミノーに反応するブラウントラウトが安易に口を使うようになる」です。水面近くのミノーに反応するブラウントラウトの2尾に1尾は、ルアーを丸呑みします。第III期は、この意味では、とても釣りやすい時期です。
しかし、良い事はこれだけでした。
第III期の第二の特徴は「ランカーの大半がシャローから消える。もしくは、ランカーの大半がミノーへの興味を失う」です。この前の第II期では「デカかった...」と確信できるショートバイトやバラしが時々起きます。しかし、ターンオーバーが完了すると同時に、こうした反応が完全に消えます。そんな訳で、第III期に入ると「ランカー狙いのミノーのシーズンが終わってしまった...」と、痛感してしまいます (なお、これはチョイ投げの水面直下のミノーに限った話であることには、くれぐれもご注意下さい) 。
こうした変化が原因で、第III期に入ると、釣果の内訳がガラリと変わります。私が経験した範囲内だと、2つのパターンがあるようです。例えば2011年から2013年までの場合、40cm台の数釣りが楽しめました。特に、ターンオーバー直後に釣果のピークがあります。このピークに当たると、サイズは40cm台が中心ですが、1回の釣行で5尾以上の釣果が得られます。
一方、2014年は全く違ってました。この年は、3〜4時間粘って反応を1回取れればラッキー...というような、えらく渋いコンディションが続きました。私はこの時期に4回通って、まともなサイズは2尾だけでした。しかし、サイズは60cmで悪くありませんでした。


こうした年による違いがあるため、この期間の一般論は難しいと感じています。以前「12月こそランカーを獲る絶好のシーズン」と豪語していた方に会ったことがあります。ですから、そういう年もあるのかもしれません。

湖水の透明度が一気に上昇したと同時に、水温が4℃前後に落ち着きます。これが、ターンオーバーが完了したことを示すサインです。例年、11月下旬から12月上旬の間のどこかで、これが突然起きます。第III期の始まりです。

私がこの4〜5年間に経験した限りでは、第III期には明確な特徴が2つあります。第一の特徴は「ミノーに反応するブラウントラウトが安易に口を使うようになる」です。水面近くのミノーに反応するブラウントラウトの2尾に1尾は、ルアーを丸呑みします。第III期は、この意味では、とても釣りやすい時期です。
しかし、良い事はこれだけでした。
第III期の第二の特徴は「ランカーの大半がシャローから消える。もしくは、ランカーの大半がミノーへの興味を失う」です。この前の第II期では「デカかった...」と確信できるショートバイトやバラしが時々起きます。しかし、ターンオーバーが完了すると同時に、こうした反応が完全に消えます。そんな訳で、第III期に入ると「ランカー狙いのミノーのシーズンが終わってしまった...」と、痛感してしまいます (なお、これはチョイ投げの水面直下のミノーに限った話であることには、くれぐれもご注意下さい) 。
こうした変化が原因で、第III期に入ると、釣果の内訳がガラリと変わります。私が経験した範囲内だと、2つのパターンがあるようです。例えば2011年から2013年までの場合、40cm台の数釣りが楽しめました。特に、ターンオーバー直後に釣果のピークがあります。このピークに当たると、サイズは40cm台が中心ですが、1回の釣行で5尾以上の釣果が得られます。
一方、2014年は全く違ってました。この年は、3〜4時間粘って反応を1回取れればラッキー...というような、えらく渋いコンディションが続きました。私はこの時期に4回通って、まともなサイズは2尾だけでした。しかし、サイズは60cmで悪くありませんでした。


こうした年による違いがあるため、この期間の一般論は難しいと感じています。以前「12月こそランカーを獲る絶好のシーズン」と豪語していた方に会ったことがあります。ですから、そういう年もあるのかもしれません。
2015年02月21日
晩秋のシーズナルパターン (その11) 第II期【水温5〜12℃】ミノーの場合
まとまった量の雪が降ると、支笏湖の水温は12℃を切ります。通常、11月上旬にこれが起こります。12℃から5℃までが第II期です。

5回前の書き込みの写真をもう1回載せます。この写真のように、緑色や白濁が濃い状態で第II期が始まり、徐々に薄まっていくのがこの時期の特徴です。しかし、こうした白濁は、薄くはなっても、第II期の間は消えることがありません。

水温が12℃を切ったと同時に、水温躍層にいたブラウントラウトの一部が、第一陣としてシャローに差してくるようです。強い低気圧が北海道を通過し、雪や強風をもたらす度に、岸から狙えるブラウントラウトの数が増えていくことを実感します。この時期、夜釣りではコンスタントな釣果が得られているようです。湖岸で出会った方と立ち話した内容を総合すると、夜釣りの場合、この第II期に、ニナル川河口から苔の洞門までの範囲で、毎年コンスタントに5尾〜10尾程度の80cm台のブラウントラウトと、1尾前後の90cm台のブラウントラウトが上がっているようです。この夢があるので、南岸沿いの国道276号線は、この時期はあちこちで、夜な夜な、沢山の車が停車しています。
しかし日中は、とんでもなく苦戦します。この時期は、特に初期、ルアーに微かに触れる程度のショートバイトが続きます。運良く「乗った!」と思っても、食いが浅く、すっぽ抜けることばかりです。「水面直下のミノーに反応するブラウントラウトがいるのに、ショートバイトばかりでルアーが見切られる」が第II期の、1つめの特徴です。ただし、辛抱強く通い込んでいると、徐々に、ルアーに口を使うブラウントラウトが増えることを実感します。
第II期のもう1つの特徴は「ブラウントラウトは気まぐれで、ウロウロ徘徊しているらしい」です。春の釣りの場合、同じエリアに何度も通えば、ブラウントラウトがルアーに反応する場所のほとんどが、限られた数カ所に集中することに気付きます。しかし晩秋のこの時期は、「ここで反応するはず」と確信できる場所のほとんどで、無反応です。しかし丁寧に探っていくと「なぜここで?」と思う場所で反応します。その上、反応する場所が釣行の度に異なります。こうした理由から「こいつら、ただ単に、ウロウロしているだけなのか?」と思うことが多いです。この傾向は、少なくとも水面直下のミノーの釣りの場合、この数年間で特に強くなりました。
第II期の3つめの特徴は「ランカーを獲るチャンス」です。この時期は渋いですが、運良く釣果に恵まれると、数尾に1尾、ランカーが混じります。2014年の私の場合、第II期に6回釣行し、20回の反応がありました。しかしフッキングしたブラウントラウトはたったの5尾。しかし2014年は運良く、そのうち1尾だけ76cmが混じってくれました。この期間に毎週通っていると、何度か「今のはデカかった...」と痛感するショートバイトやバラシを経験します。私の技量だと、限りなく100%に近い確率で、こうしたランカーを逃します。この写真の76cmの場合も、「獲った」と確信できる魚ではなく、運良く偶然釣れてくれた魚でした。

以上を一言でまとめると「第II期は難易度が高いからこそ、やりがいのある時期」と言えると思います。ただし、私自身はこの時期の攻略法を全く見出せていません。この時期は、ミノーのチョイ投げでも、かなりの数のランカーにミノーを見られていることを感じます。本来なら、ランカーを量産できていいはずの時期です。しかし、彼らに口を使わす術を持ちません。ですから「自分の下手さ加減を思い知らされる、1年間でもっともみじめな時期」でもあります。

5回前の書き込みの写真をもう1回載せます。この写真のように、緑色や白濁が濃い状態で第II期が始まり、徐々に薄まっていくのがこの時期の特徴です。しかし、こうした白濁は、薄くはなっても、第II期の間は消えることがありません。

水温が12℃を切ったと同時に、水温躍層にいたブラウントラウトの一部が、第一陣としてシャローに差してくるようです。強い低気圧が北海道を通過し、雪や強風をもたらす度に、岸から狙えるブラウントラウトの数が増えていくことを実感します。この時期、夜釣りではコンスタントな釣果が得られているようです。湖岸で出会った方と立ち話した内容を総合すると、夜釣りの場合、この第II期に、ニナル川河口から苔の洞門までの範囲で、毎年コンスタントに5尾〜10尾程度の80cm台のブラウントラウトと、1尾前後の90cm台のブラウントラウトが上がっているようです。この夢があるので、南岸沿いの国道276号線は、この時期はあちこちで、夜な夜な、沢山の車が停車しています。
しかし日中は、とんでもなく苦戦します。この時期は、特に初期、ルアーに微かに触れる程度のショートバイトが続きます。運良く「乗った!」と思っても、食いが浅く、すっぽ抜けることばかりです。「水面直下のミノーに反応するブラウントラウトがいるのに、ショートバイトばかりでルアーが見切られる」が第II期の、1つめの特徴です。ただし、辛抱強く通い込んでいると、徐々に、ルアーに口を使うブラウントラウトが増えることを実感します。
第II期のもう1つの特徴は「ブラウントラウトは気まぐれで、ウロウロ徘徊しているらしい」です。春の釣りの場合、同じエリアに何度も通えば、ブラウントラウトがルアーに反応する場所のほとんどが、限られた数カ所に集中することに気付きます。しかし晩秋のこの時期は、「ここで反応するはず」と確信できる場所のほとんどで、無反応です。しかし丁寧に探っていくと「なぜここで?」と思う場所で反応します。その上、反応する場所が釣行の度に異なります。こうした理由から「こいつら、ただ単に、ウロウロしているだけなのか?」と思うことが多いです。この傾向は、少なくとも水面直下のミノーの釣りの場合、この数年間で特に強くなりました。
第II期の3つめの特徴は「ランカーを獲るチャンス」です。この時期は渋いですが、運良く釣果に恵まれると、数尾に1尾、ランカーが混じります。2014年の私の場合、第II期に6回釣行し、20回の反応がありました。しかしフッキングしたブラウントラウトはたったの5尾。しかし2014年は運良く、そのうち1尾だけ76cmが混じってくれました。この期間に毎週通っていると、何度か「今のはデカかった...」と痛感するショートバイトやバラシを経験します。私の技量だと、限りなく100%に近い確率で、こうしたランカーを逃します。この写真の76cmの場合も、「獲った」と確信できる魚ではなく、運良く偶然釣れてくれた魚でした。

以上を一言でまとめると「第II期は難易度が高いからこそ、やりがいのある時期」と言えると思います。ただし、私自身はこの時期の攻略法を全く見出せていません。この時期は、ミノーのチョイ投げでも、かなりの数のランカーにミノーを見られていることを感じます。本来なら、ランカーを量産できていいはずの時期です。しかし、彼らに口を使わす術を持ちません。ですから「自分の下手さ加減を思い知らされる、1年間でもっともみじめな時期」でもあります。
2015年02月21日
晩秋のシーズナルパターン (その10) 第I期【水温12℃以上】ミノーの場合
ここから3回の書き込みで、ミノーで水面直下(水面から50cm以内)を狙った場合の、魚の反応の変化を書きます。スプーンやメタルジグで深い泳層を狙う方々とは、感じる変化が異なると思います。これ以降の記述は、あくまで「着水と同時にルアーを動かす水面付近の釣り」であること、ご了承下さい。
まず第I期です。10月から11月初旬にかけて、支笏湖の水温が1週間で1〜2℃程度のペースでなだらかに低下します。しかし12℃前後になったところで、水温低下が非常に緩やかになります。まとまった量の雪が降り、水温が12℃をはっきり切るまでの期間が第I期です。

ブラウントラウトの一部は、9月からシャローにいます。しかし10月は、湖面に落下する昆虫(主に小さい蛾やカメムシ)を完全に偏食しています。「ブラウントラウトがミノーをほぼ完全に無視する」が第I期の特徴です。水深1m以内のシャローをうろつくブラウントラウトを観察していると、落下した昆虫を見つける度、ボシャンッ!と水柱を立てて補食しています。ミノーを投げると、着水と同時に近寄りますが、動かすと同時に去っていきます。10月のブラウントラウトは、ドライフライの独断場です。この時期、フライの方々は、本当によく釣っています。
この時期、ルアーで確実に狙えるのはニジマスです。10月から11月中旬は、シャローでの荒食いの時期のようです。餌を探して水面近くや、水深50cm以内の岸際をウロウロするニジマスを見ることがあります。この時期のニジマスは、湖底の地形変化や実績ポイントなどお構いなしに、あちこちをウロウロします。べた凪の日は、背びれを水面から出して徘徊することもあります。見つけたら簡単で、ニジマスから3〜5m程度離れた場所にルアーを着水させます。着水と同時に、ニジマスは一目散にルアーに直行します。そして、ルアーを動かすと同時にヒットします。ルアーは、ミノーでもスプーンでもスピナーでも、何でもOKです。確実に食わせるには、小さめのルアーを使うのがコツです。
まず第I期です。10月から11月初旬にかけて、支笏湖の水温が1週間で1〜2℃程度のペースでなだらかに低下します。しかし12℃前後になったところで、水温低下が非常に緩やかになります。まとまった量の雪が降り、水温が12℃をはっきり切るまでの期間が第I期です。

ブラウントラウトの一部は、9月からシャローにいます。しかし10月は、湖面に落下する昆虫(主に小さい蛾やカメムシ)を完全に偏食しています。「ブラウントラウトがミノーをほぼ完全に無視する」が第I期の特徴です。水深1m以内のシャローをうろつくブラウントラウトを観察していると、落下した昆虫を見つける度、ボシャンッ!と水柱を立てて補食しています。ミノーを投げると、着水と同時に近寄りますが、動かすと同時に去っていきます。10月のブラウントラウトは、ドライフライの独断場です。この時期、フライの方々は、本当によく釣っています。
この時期、ルアーで確実に狙えるのはニジマスです。10月から11月中旬は、シャローでの荒食いの時期のようです。餌を探して水面近くや、水深50cm以内の岸際をウロウロするニジマスを見ることがあります。この時期のニジマスは、湖底の地形変化や実績ポイントなどお構いなしに、あちこちをウロウロします。べた凪の日は、背びれを水面から出して徘徊することもあります。見つけたら簡単で、ニジマスから3〜5m程度離れた場所にルアーを着水させます。着水と同時に、ニジマスは一目散にルアーに直行します。そして、ルアーを動かすと同時にヒットします。ルアーは、ミノーでもスプーンでもスピナーでも、何でもOKです。確実に食わせるには、小さめのルアーを使うのがコツです。
2015年02月21日
晩秋のシーズナルパターン (その9) 水温に基づいた3分類
ターンオーバーを観察するもう一つの方法は、水温測定です。2014年の実測データを実例に、晩秋の水温低下を見てもらいます (下図)。

水温の経時変化を、湖の変化と、魚のルアーへの反応の変化に対応させて、3つに分類します。仰々しい名称ですが、とりあえず、第I期、第II期、第III期と呼ぶことにします。
3分類したそれぞれを紹介します。10月から11月上旬まで、水温がなだらかに低下し、12℃前後で落ち着きます (下図)。これが第I期です。この期間は、水深20m程度の深さに、水温躍層がしっかりと維持されています。水面付近の湖水は、緑色が濃く、淡い白濁があります。

11月上旬から、水温が下がったり上がったり、ジグザグしながら12℃前後から5℃前後まで低下します (下図)。これが第II期です。この期間、ガツガツとターンオーバーが進行し、徐々に水温躍層が壊れていきます。水面付近の湖水の緑色や淡い白濁は、少しずつ薄くなっていきます。

第II期について、もう少し書きます。この時期、水温がジグザグと変化する原因は降雪です。特に、報道ステーションやNews ZEROのような全国ネットのニュース番組の冒頭で「東日本が寒波に覆われます。北日本では暴風雪の可能性があります」というニュースが流れると、支笏湖でも、まとまった量の雪が降り、強風が吹き荒れます。2014年の初冬は、こうした降雪が3回ありました (下図)。その度に、支笏湖の水温が大きく低下しました (下図)。

例年だと、11月下旬から12月上旬にかけて、水温は4℃前後に落ち着きます。これが
第III期です。水温4℃になると、水温躍層が消失し、完全にターンオーバーが完了したと判断できます。水面付近の湖水の透明度が一気に上昇します。

水温の経時変化を、湖の変化と、魚のルアーへの反応の変化に対応させて、3つに分類します。仰々しい名称ですが、とりあえず、第I期、第II期、第III期と呼ぶことにします。
3分類したそれぞれを紹介します。10月から11月上旬まで、水温がなだらかに低下し、12℃前後で落ち着きます (下図)。これが第I期です。この期間は、水深20m程度の深さに、水温躍層がしっかりと維持されています。水面付近の湖水は、緑色が濃く、淡い白濁があります。

11月上旬から、水温が下がったり上がったり、ジグザグしながら12℃前後から5℃前後まで低下します (下図)。これが第II期です。この期間、ガツガツとターンオーバーが進行し、徐々に水温躍層が壊れていきます。水面付近の湖水の緑色や淡い白濁は、少しずつ薄くなっていきます。

第II期について、もう少し書きます。この時期、水温がジグザグと変化する原因は降雪です。特に、報道ステーションやNews ZEROのような全国ネットのニュース番組の冒頭で「東日本が寒波に覆われます。北日本では暴風雪の可能性があります」というニュースが流れると、支笏湖でも、まとまった量の雪が降り、強風が吹き荒れます。2014年の初冬は、こうした降雪が3回ありました (下図)。その度に、支笏湖の水温が大きく低下しました (下図)。

例年だと、11月下旬から12月上旬にかけて、水温は4℃前後に落ち着きます。これが

第III期です。水温4℃になると、水温躍層が消失し、完全にターンオーバーが完了したと判断できます。水面付近の湖水の透明度が一気に上昇します。
2015年02月21日
晩秋のシーズナルパターン (その8) ターンオーバー (7)
目視でターンオーバーの進行を観察するための、残りの方法を書きます。
■方法2■
これは、バス釣りでよく行う方法です。ロッドティップを湖水に入れます。

次いで、砂糖やミルクを入れたコーヒーを撹拌する要領で、少し激しく撹拌します。

すると直径1〜2cm程度の泡が水面に生じます。水温躍層が残っている時は、この泡が10秒程度待っても全く消えないことが多いです。バス釣りの場合「泡が残れば悪いコンディションの水」「泡が消えれば良いコンディションの水」と判断します。支笏湖でも、ブラウントラウトの場合、良い水で良い反応が得られます。一方、ニジマスの反応は、この方法での判断とは無関係のようです。ターンオーバーの数週間前になると、この泡は1秒ももたずに消えてしまいます。「泡が消えればターンオーバー完了が近づいてきた」と判断できます。
■方法3■
支笏湖では、8〜9月になると、風下に、海釣りの人が「潮目」と呼ぶのに似た、帯状の泡が現れ始めます。支笏湖では、強い風は低気圧通過後の西風や北西風が多いため、旧有料道路でこの泡を見る機会が増えます。ターンオーバーの数週間前になると、この泡(潮目)が著しく減ります。ターンオーバーが完了すると、完全に消えます。ただし、1つだけ注意があります。ターンオーバー前の旧有料道路でこの泡を見れるのは、西風の時だけです。

■方法4■
ターンオーバーの数週間前になると、風が吹きたまりやすい場所に、水面に散らばった泡が急に増えます。また、細かい泡が岸に打ち上げられたりします。経験上、これを観察した数週間後にはターンオーバーがほぼ完了します。何故これが起こるのか分かりません。2012年に気付き、それ以降毎年観察していますが、少なくともこれを書いてる2014年まで、毎年必ずこれが起きています。こうした泡を見かけると「あと数週間で本番が来る」と確信できます。


■方法2■
これは、バス釣りでよく行う方法です。ロッドティップを湖水に入れます。

次いで、砂糖やミルクを入れたコーヒーを撹拌する要領で、少し激しく撹拌します。

すると直径1〜2cm程度の泡が水面に生じます。水温躍層が残っている時は、この泡が10秒程度待っても全く消えないことが多いです。バス釣りの場合「泡が残れば悪いコンディションの水」「泡が消えれば良いコンディションの水」と判断します。支笏湖でも、ブラウントラウトの場合、良い水で良い反応が得られます。一方、ニジマスの反応は、この方法での判断とは無関係のようです。ターンオーバーの数週間前になると、この泡は1秒ももたずに消えてしまいます。「泡が消えればターンオーバー完了が近づいてきた」と判断できます。
■方法3■
支笏湖では、8〜9月になると、風下に、海釣りの人が「潮目」と呼ぶのに似た、帯状の泡が現れ始めます。支笏湖では、強い風は低気圧通過後の西風や北西風が多いため、旧有料道路でこの泡を見る機会が増えます。ターンオーバーの数週間前になると、この泡(潮目)が著しく減ります。ターンオーバーが完了すると、完全に消えます。ただし、1つだけ注意があります。ターンオーバー前の旧有料道路でこの泡を見れるのは、西風の時だけです。

■方法4■
ターンオーバーの数週間前になると、風が吹きたまりやすい場所に、水面に散らばった泡が急に増えます。また、細かい泡が岸に打ち上げられたりします。経験上、これを観察した数週間後にはターンオーバーがほぼ完了します。何故これが起こるのか分かりません。2012年に気付き、それ以降毎年観察していますが、少なくともこれを書いてる2014年まで、毎年必ずこれが起きています。こうした泡を見かけると「あと数週間で本番が来る」と確信できます。


2015年02月21日
晩秋のシーズナルパターン (その7) ターンオーバー (6)
ターンオーバーによって、湖水の淡い白濁が消える理由を説明します。まず、今までの図を、実際のスケールにあわせて描き直します (下図)。支笏湖は水深360mあります。表水層は20m程度なので、深水層はその約17倍です。表水層は、支笏湖の湖水のごく一部であることが分かります。

表水層では、夏から秋にかけて、植物プランクトン・ウィード(水草)・付着藻類が繁茂し、これを餌にする動物プランクトンが繁殖します。その結果、生きた動物プランクトン、動物プランクトンや植物プランクトンの死骸、枯死したウィードや付着藻類が分解される過程でできた有機物の微細な欠片等が表水層内に漂います。その結果、表水層の水が、淡い白濁をまといます。また、植物プランクトン由来の緑色が強いです。
一方、深水層は、十分な光が届かない深さ(20m前後)から始まり、最深部360mまで続きます。その上、水温は4℃前後で低いです。その上、貧栄養湖です。そこで、深水層ではプランクトンや微生物の活動が著しく抑制されます。この結果、表水層と比べて相対的に、無色透明な湖水のままでいます。
以上を下図にまとめました。

この結果、ターンオーバーによって表水層と深水層が混ざり合うと、表水層の白濁が深水層の無色透明に希釈されます。そして、ターンオーバーとともに、シャローの水の透明度が一気に上昇し、淡い白濁が完全に消えます (下図)。

こうした理由から、ターンオーバーの進行具合や、ターンオーバーの完了を観察するには、偏光グラスを使った目視が確実な方法です。

表水層では、夏から秋にかけて、植物プランクトン・ウィード(水草)・付着藻類が繁茂し、これを餌にする動物プランクトンが繁殖します。その結果、生きた動物プランクトン、動物プランクトンや植物プランクトンの死骸、枯死したウィードや付着藻類が分解される過程でできた有機物の微細な欠片等が表水層内に漂います。その結果、表水層の水が、淡い白濁をまといます。また、植物プランクトン由来の緑色が強いです。
一方、深水層は、十分な光が届かない深さ(20m前後)から始まり、最深部360mまで続きます。その上、水温は4℃前後で低いです。その上、貧栄養湖です。そこで、深水層ではプランクトンや微生物の活動が著しく抑制されます。この結果、表水層と比べて相対的に、無色透明な湖水のままでいます。
以上を下図にまとめました。

この結果、ターンオーバーによって表水層と深水層が混ざり合うと、表水層の白濁が深水層の無色透明に希釈されます。そして、ターンオーバーとともに、シャローの水の透明度が一気に上昇し、淡い白濁が完全に消えます (下図)。

こうした理由から、ターンオーバーの進行具合や、ターンオーバーの完了を観察するには、偏光グラスを使った目視が確実な方法です。
2015年02月21日
晩秋のシーズナルパターン (その6) ターンオーバー (5)
ターンオーバーの概説を終えました。今度は、ターンオーバーの進行を観察する方法について書きます。目視による方法と、水温を測定する方法があります。両方併用するのが確実です。
目視する方法から説明します。湖水の透明度に注目します。経験を重ねると「今日はブラウンは絶対に駄目。ニジマスと遭遇するチャンスを待つしかない」とか「今日は渋くてショートバイトが多発しそう」とか「今日は、釣れないはずが絶対にない」といった判断を下せるようになります。
■方法1■
基本となる方法は、偏光グラスを使って、水深50cmから1mの湖水を観察することです。慣れないうちは、べた凪に近い場所を探し、膝から腰の深さ(50cm〜1m)までウェーディングして、足下とその周囲を観察するのがよいです。この方法なら、かつべた凪だったら、偏光グラスなしで透明度を見抜けます。
以下、写真を計7枚見てもらいます。全て、薄曇り〜曇天かつ波が弱い条件で撮影しました。全ての写真は、PLフィルタ(偏光フィルタ)を使って撮影しています。
まず、同じ場所で撮影した2枚を見比べて下さい。1枚目は、ターンオーバー前の11月上旬の写真です。

湖水の緑色が濃いこと、白濁した感じの淡い濁りがあることが分かります。次に、ターンオーバー完了直後の、12月上旬の写真です。

この2枚、完全に違うことが分かります。緑色が薄まり、白濁が完全に消え、透明度が一気に上昇します。ターンオーバーによって、水面付近の湖水が、ここまで大胆に変化します。
復習のため、あと5枚見てもらいます。以下の2枚は、ターンオーバー直前の、シャローの湖水の様子です。PLフィルタの偏光効果が最大限効き、空の映り込みを完全に除去できた部分を、白枠で囲っています。この部分に注意してみて下さい。


この2枚を見ると、淀んだ感じの淡い白濁があることが分かります。
次いで、ターンオーバー後の写真を3枚見てもらいます。



「これぞ支笏湖の澄んだ水だっ!」と言いたくなるような、無色透明な水になっています。11月に毎週末 支笏湖に通っていると、湖水の淡い白濁が少しずつ弱くなりますが、しかしなかなか、白濁が完全に消えません。ところが、ある日 突然、無色透明な水に変化します。これがターンオーバー完了の合図です。
こうした湖水の変化に、何故か、ブラウントラウトのルアーへの反応の変化が対応します。ターンオーバー前の、淡く白濁したコンディションでは、ルアーへの反応が悪いです。ルアーを追尾するだけだったり、微かなショートバイトが多発します。ルアーに反応するブラウントラウトの5尾に1尾、もしくは10尾に1尾程度しか、フッキングに至りません。この時期、風が吹き、波が立つとフッキングする確率が上昇しますが、それでも、ショートバイトに悩まされ続けます。
ところが、ターンオーバーが完了して、湖水が透明になると、ショートバイトが激減し、ルアーに反応するブラウントラウトの2尾に1尾は、ルアーを丸呑みするようになります。この3〜4年間、ターンオーバーが湖水の透明度の変化を伴うことを発見してから、透明度の変化とルアーへの反応の変化をずっと観察し続けてきました。この3〜4年間、常に、このルールが成立しています。
最後に、2つ補足をします。1つめ。湖水の透明度の見極めは、ある程度の経験が必要です。偏光グラスを使っても、晴れた日は水面がキラキラするため湖水が透明に見えがちです。逆に、曇った日は水面が雲の白を映し出すので湖水が白濁して見えがちです。また、べた凪では白濁して見えがち、波が出ると透明に見えがちです。ですから、コツを掴むまでは練習が必要です。ただし、コツを掴めば、偏光グラスがなくても判断できるようになります。
第二に、この方法は支笏湖特有です。支笏湖は貧栄養湖です。もともと透明度が高く、水深が最深部で360mと深いです。この3つの特徴を備えているため、こうした目視による観察が可能になります。おそらく、他の湖では使えません。
目視する方法から説明します。湖水の透明度に注目します。経験を重ねると「今日はブラウンは絶対に駄目。ニジマスと遭遇するチャンスを待つしかない」とか「今日は渋くてショートバイトが多発しそう」とか「今日は、釣れないはずが絶対にない」といった判断を下せるようになります。
■方法1■
基本となる方法は、偏光グラスを使って、水深50cmから1mの湖水を観察することです。慣れないうちは、べた凪に近い場所を探し、膝から腰の深さ(50cm〜1m)までウェーディングして、足下とその周囲を観察するのがよいです。この方法なら、かつべた凪だったら、偏光グラスなしで透明度を見抜けます。
以下、写真を計7枚見てもらいます。全て、薄曇り〜曇天かつ波が弱い条件で撮影しました。全ての写真は、PLフィルタ(偏光フィルタ)を使って撮影しています。
まず、同じ場所で撮影した2枚を見比べて下さい。1枚目は、ターンオーバー前の11月上旬の写真です。

湖水の緑色が濃いこと、白濁した感じの淡い濁りがあることが分かります。次に、ターンオーバー完了直後の、12月上旬の写真です。

この2枚、完全に違うことが分かります。緑色が薄まり、白濁が完全に消え、透明度が一気に上昇します。ターンオーバーによって、水面付近の湖水が、ここまで大胆に変化します。
復習のため、あと5枚見てもらいます。以下の2枚は、ターンオーバー直前の、シャローの湖水の様子です。PLフィルタの偏光効果が最大限効き、空の映り込みを完全に除去できた部分を、白枠で囲っています。この部分に注意してみて下さい。


この2枚を見ると、淀んだ感じの淡い白濁があることが分かります。
次いで、ターンオーバー後の写真を3枚見てもらいます。



「これぞ支笏湖の澄んだ水だっ!」と言いたくなるような、無色透明な水になっています。11月に毎週末 支笏湖に通っていると、湖水の淡い白濁が少しずつ弱くなりますが、しかしなかなか、白濁が完全に消えません。ところが、ある日 突然、無色透明な水に変化します。これがターンオーバー完了の合図です。
こうした湖水の変化に、何故か、ブラウントラウトのルアーへの反応の変化が対応します。ターンオーバー前の、淡く白濁したコンディションでは、ルアーへの反応が悪いです。ルアーを追尾するだけだったり、微かなショートバイトが多発します。ルアーに反応するブラウントラウトの5尾に1尾、もしくは10尾に1尾程度しか、フッキングに至りません。この時期、風が吹き、波が立つとフッキングする確率が上昇しますが、それでも、ショートバイトに悩まされ続けます。
ところが、ターンオーバーが完了して、湖水が透明になると、ショートバイトが激減し、ルアーに反応するブラウントラウトの2尾に1尾は、ルアーを丸呑みするようになります。この3〜4年間、ターンオーバーが湖水の透明度の変化を伴うことを発見してから、透明度の変化とルアーへの反応の変化をずっと観察し続けてきました。この3〜4年間、常に、このルールが成立しています。
最後に、2つ補足をします。1つめ。湖水の透明度の見極めは、ある程度の経験が必要です。偏光グラスを使っても、晴れた日は水面がキラキラするため湖水が透明に見えがちです。逆に、曇った日は水面が雲の白を映し出すので湖水が白濁して見えがちです。また、べた凪では白濁して見えがち、波が出ると透明に見えがちです。ですから、コツを掴むまでは練習が必要です。ただし、コツを掴めば、偏光グラスがなくても判断できるようになります。
第二に、この方法は支笏湖特有です。支笏湖は貧栄養湖です。もともと透明度が高く、水深が最深部で360mと深いです。この3つの特徴を備えているため、こうした目視による観察が可能になります。おそらく、他の湖では使えません。
2015年02月21日
晩秋のシーズナルパターン (その5) ターンオーバー (4)
次いで、ターンオーバー前後での魚の分布について書きます。
10年以上前に、退屈きわまりない測定を行ってみました。ゴムボートに、広い探査範囲をもつEagle社のTriFinderという魚探を乗せました(当時の欧米のレイクトローラー達の必須の道具でした)。で、オコタンから美笛までの範囲を5時間以上ウロウロしました。

TriFinderが魚を感知すると、画面にフィッシュマークが現れ、その水深を表示してくれます。そこで、その水深をメモします。5時間以上もこの作業を続けると、200以上のフィッシュマークが現れます。その全てを記録しました。
この作業を、ターンオーバー直前と直後に行ってみました。
水温躍層まだ残っているターンオーバー直前(10月下旬)は、TriFinderが感知した魚の80%以上が、水深3mから30mの範囲に現れました (下図の左)。

加えて、この範囲の中に、2つ、特に魚が集中している泳層がありました。水深3mから8mと、水深20mから26mです (下図の左)。

水温躍層が形成されている期間、大半のブラウントラウトは水温躍層前後の水深にいることが知られています (e.g., D.C. Nettles, J.M. Haynes, R.A. Olson, and J.D. Winter (1987) Seasonal Movements and Habitats of Brown Trout in Southcentral Lake Ontario. Journal of Great Lake Research. 13: 168-177.)。そこで、水深20〜26mで探知された魚の大半がブラウントラウトである可能性が高いです。
一方、3〜8mの泳層は、日光がよく浸透する範囲です (ボートから偏光グラスを使って湖を覗くと、水深7〜8mまではくっきりと湖底が観察できます)。そこで、植物プランクトンやウィードが繁茂し、ブラウントラウトの餌となるベイトフィッシュの格好の餌場かつ隠れ家となっていると想像できます。
次いで、ターンオーバー直後(11月中旬)の、フィッシュマークの分布を示します。まず、TriFinderが感知した魚の80%以上が、水深3mから18mの範囲に現れました (下図の右)。

加えて、水深18m以浅の魚の70%は、水深3mから8mに集中します。

以上をまとめます。アメリカの釣り雑誌やトラウトの釣りの教科書で頻繁に行われている説明は以下の通りです。「初夏から晩秋にかけて水温躍層付近にいたブラウントラウトやレイクトラウトは、ターンオーバーの進行とともに、ベイトに富んだシャローに侵入し、荒食いを始める。これが理由で、ターンオーバーが始まると、ブラウントラウトやレイクトラウトの岸釣りのシーズンが始まる。」

10年以上前に、退屈きわまりない測定を行ってみました。ゴムボートに、広い探査範囲をもつEagle社のTriFinderという魚探を乗せました(当時の欧米のレイクトローラー達の必須の道具でした)。で、オコタンから美笛までの範囲を5時間以上ウロウロしました。

TriFinderが魚を感知すると、画面にフィッシュマークが現れ、その水深を表示してくれます。そこで、その水深をメモします。5時間以上もこの作業を続けると、200以上のフィッシュマークが現れます。その全てを記録しました。
この作業を、ターンオーバー直前と直後に行ってみました。
水温躍層まだ残っているターンオーバー直前(10月下旬)は、TriFinderが感知した魚の80%以上が、水深3mから30mの範囲に現れました (下図の左)。

加えて、この範囲の中に、2つ、特に魚が集中している泳層がありました。水深3mから8mと、水深20mから26mです (下図の左)。

水温躍層が形成されている期間、大半のブラウントラウトは水温躍層前後の水深にいることが知られています (e.g., D.C. Nettles, J.M. Haynes, R.A. Olson, and J.D. Winter (1987) Seasonal Movements and Habitats of Brown Trout in Southcentral Lake Ontario. Journal of Great Lake Research. 13: 168-177.)。そこで、水深20〜26mで探知された魚の大半がブラウントラウトである可能性が高いです。
一方、3〜8mの泳層は、日光がよく浸透する範囲です (ボートから偏光グラスを使って湖を覗くと、水深7〜8mまではくっきりと湖底が観察できます)。そこで、植物プランクトンやウィードが繁茂し、ブラウントラウトの餌となるベイトフィッシュの格好の餌場かつ隠れ家となっていると想像できます。
次いで、ターンオーバー直後(11月中旬)の、フィッシュマークの分布を示します。まず、TriFinderが感知した魚の80%以上が、水深3mから18mの範囲に現れました (下図の右)。

加えて、水深18m以浅の魚の70%は、水深3mから8mに集中します。

以上をまとめます。アメリカの釣り雑誌やトラウトの釣りの教科書で頻繁に行われている説明は以下の通りです。「初夏から晩秋にかけて水温躍層付近にいたブラウントラウトやレイクトラウトは、ターンオーバーの進行とともに、ベイトに富んだシャローに侵入し、荒食いを始める。これが理由で、ターンオーバーが始まると、ブラウントラウトやレイクトラウトの岸釣りのシーズンが始まる。」

2015年02月21日
晩秋のシーズナルパターン (その4) ターンオーバー (3)
もう一回だけターンオーバーの基礎を続けます。ここでは、ターンオーバー前後での水温分布について書きます。
水温躍層が存在する期間、表水層の水温は季節によって変化します。8月中旬なら25℃近くまで上昇します。ターンオーバー直前の10月下旬なら、10℃近くまで低下します。一方、深水層の水温は、常に4℃前後です (下図の左)。これは、水の密度が4℃で最も高くなることを反映しています。

一方、ターンオーバーした状態では、基本的に水面から湖の最深部まで、4℃前後の水温で一定になります (下図の右)。ただし、水面近くの数mはその日の気温に影響されるため、私が測定した範囲だと、数℃以内の範囲で、変動します。

水温躍層が存在する期間、表水層の水温は季節によって変化します。8月中旬なら25℃近くまで上昇します。ターンオーバー直前の10月下旬なら、10℃近くまで低下します。一方、深水層の水温は、常に4℃前後です (下図の左)。これは、水の密度が4℃で最も高くなることを反映しています。

一方、ターンオーバーした状態では、基本的に水面から湖の最深部まで、4℃前後の水温で一定になります (下図の右)。ただし、水面近くの数mはその日の気温に影響されるため、私が測定した範囲だと、数℃以内の範囲で、変動します。

2015年02月21日
晩秋のシーズナルパターン (その3) ターンオーバー (2)
ターンオーバーの基礎を続けます。ここでは、ターンオーバー前後での湖水の循環について書きます。
支笏湖に、左から右へ風が吹いたとします (下図)。最初に、水温躍層が形成されている条件を考えます。

風は水の流れを生み、表水層内に時計回りの流れが発生します (下図の左)。

さらに、表水層内の流れは水温躍層での摩擦を生み、その結果、深水層内に反時計回りの流れを生みます (下図の左)。

次いで、ターンオーバーした状態での流れを見てみます。この場合、湖水全体を巻き込んだ、時計回りの流れのみが生じます (下図の右)。

支笏湖に、左から右へ風が吹いたとします (下図)。最初に、水温躍層が形成されている条件を考えます。

風は水の流れを生み、表水層内に時計回りの流れが発生します (下図の左)。

さらに、表水層内の流れは水温躍層での摩擦を生み、その結果、深水層内に反時計回りの流れを生みます (下図の左)。

次いで、ターンオーバーした状態での流れを見てみます。この場合、湖水全体を巻き込んだ、時計回りの流れのみが生じます (下図の右)。