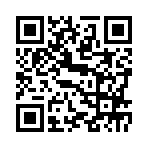2018年05月28日
モンスター
またも、モンスターの捕獲情報です。前回の釣行で、美笛の林道のゲートで出会った、苫小牧の安藤さんという方から、写真を送って頂きました。4月15日の釣果だそうです。デップリしたお腹で、美しい魚体で、見ててうっとりする写真です。写真を提供して下さって、ありがとうございました。「こういう魚を獲るために、自分も、他の方も、頑張ってこの湖に通うんだよな...」と、しみじみと感じさせてもらいました。




2018年05月26日
支笏湖2018年5月26日
方法:岸からの釣り
月齢:11
気温:日平均●℃ (●~●℃)
水温:7.8℃ (7.1〜8.9℃)
時間:8時間 (午前9時〜午後6時)
反応:5回
釣果:3尾
「やばい。あと1ヶ月で春〜初夏シーズンが終わる」と、焦りながらの釣行。内心「1本は、80cm台を獲っておきたい。いやっ、70cm台でもいい」と、ほんのり焦っていた。この日は午前9時から強めの北北西の風が吹く予報だった。これを信じ、南岸に行き、駐車スペースを探した。午前9時に支寒内で開始。予報は外れて、穏やかな湖面だった。水温7.1℃。

「2週間前のこともある。やるよっ!。叩くよっ!」と自分に言い聞かせて開始。ところが、全く反応がない。2時間かけてトンネルまで叩き続けたのに、ショートバイトもない。追尾もない。エビもない。何も無かった。「これは、ちょっと異常過ぎる。この湖面ではあっても、あり得ない」と感じた。
「どうする?」と考え「ニナルの手前のワンドを叩く」と決めた。ここは、今年に入って2回、ほぼべた凪でも数尾のヒットがあった。午前11時半、これまで反応が集中した30m程度を叩いた。湖面は、支寒内より、ましだった。水温8.9℃。「このワンドでこの波があれば十分」と思えた。しかし、何もない。「マジッ?」という印象。そこで、ワンド全体を、2時間かけて等間隔で全部叩いた。しかし何もなかった。「アッパレ」と苦笑いするしかない無反応だった。

ここで「今日の月齢11は、フローティングミノーの釣りと相性が悪いかもしれない...」という疑問が生まれた。それならそれで、とことん、無反応を確認する必要がある。となると「波がある場所を探して、そこで数時間叩いて、完全な無反応を確認する必要がある」と判断。
車で、国道276号線を走り、所々で停車して湖面を見て回ったが「この波なら十分!」と思える場所がなかった。アメダスを見ると、天気予報とは正反対の「南東風」が吹き始めていた。「これなら丸駒が向い風になる」と判断し、このエリアに賭けることにした。波はあまり強くない。しかし、何とか食わせられそうな波だった。午後2時過ぎに開始。

開始1時間後「そろそろピックアップ」というタイミングの、岸から3〜4mの所で、いきなり「ドボンッ!」と、 凄い音の水柱が立ち、「はっ?。何これっ?」と思って見ていたら、ロッドが絞り込まれた。61cmのブラウントラウトだった(15:21)。


乗ったのは、三角印の場所。水深は20〜30cm。「こんな事が日中に起こるんだ...」と、初めて経験する乗り方に驚いた。夜釣りのトップウォーターへの反応のようだった。

さらに約1時間後、ゆっくり重みが乗り、ドラグからジリジリとラインが引き出された。久しぶりの重量感だった。「やったよ!。1年半ぶりの80cm台の引き方だよっ!」と喜んだ。ゆっくりと、やり取りし、ネットに入れた。入れた瞬間、70cmのフレームから、尾っぽが20cm近くはみ出している。「間違いない!。80cm台半ばはある」。ところが、ネットを持ち上げる瞬間、激しく暴れ出し、フックが折れ、ネットから飛び出し、逃げられてしまった...。茫然自失。
「ネットに入れた魚に逃げられる馬鹿が、どこの世界におっとや!。馬鹿か?貴様は!」と、怒りで一杯になった。
原因は簡単だった。今年、トレブルフックの付いたフローティングミノーを使う機会が増え、ラバーネットの必要性を感じていた。しかし「これだよ!これっ!」と思える製品が無かった。結局、ウォーターランドのメータースッポリネットという製品を購入し、ネットを外して、シーバス用のフレームに付けていた。しかし、このメータースッポリネットが、あまりにも浅かった。80cm台半ばになると、全くスッポリ入らない。逃げ出された瞬間、頭も尾っぽも5〜10cmずつ、はみ出していた。おまけに、フレームの付け根が、魚の重みと激しい暴れ方で、ひん曲がってしまった。このラバーネットが届いた時「これで、本当に80cmが入るのか?」と不安に感じたが、まさしく、不安通りの結果となってしまった。
頭を冷やせば、このランディングネットなら、ネットの操作を第三者に任せない限り、起こっても当たり前のことが、起こっただけだった...。「マーフィーの法則は正しかった」と思い知らされた。完全に自業自得。
これで完全に腹が立ち「絶対にもう1尾、獲ってやる」と躍起になり、叩ける所を全て叩いた。しかし、駄目だった。3回反応があり、1回は首振りで外れた。重みから60cmあるかないか程度。ネットに収められたのは、40cmちょっとと50cm前後の2尾。


午後6時半、叩く場所が無くなり、終了。
今日学んだことは2つ。1つは、当たり前のことだが、波だった。今日は、波が弱い場所では何の反応もなかった。ある程度の波がある場所を探せば、反応があった。この日の丸駒は「波が強めになったり、弱くなったり」を繰り返した。80cm台が乗ったのは、ちょうど、この日一番に波が強くなったタイミングだった。丸駒は、4〜5年前まで散々通い込んだエリアだった。ブラウントラウトが着きやすい場所は把握しているつもりだった。しかし、この魚が乗ったのは、これまで全く反応を得られなかった場所だった。「結局、波が強くなれば、どこにだってチャンスはある」と感じた。もう1つ学んだことは、ランディングネットの重要性。単独釣行の場合、念には念を入れた製品の選択と購入が、絶対に必要。

天気図は日本気象協会(http://www.tenki.jp/guide/chart/)を引用。
月齢:11
気温:日平均●℃ (●~●℃)
水温:7.8℃ (7.1〜8.9℃)
時間:8時間 (午前9時〜午後6時)
反応:5回
釣果:3尾
「やばい。あと1ヶ月で春〜初夏シーズンが終わる」と、焦りながらの釣行。内心「1本は、80cm台を獲っておきたい。いやっ、70cm台でもいい」と、ほんのり焦っていた。この日は午前9時から強めの北北西の風が吹く予報だった。これを信じ、南岸に行き、駐車スペースを探した。午前9時に支寒内で開始。予報は外れて、穏やかな湖面だった。水温7.1℃。

「2週間前のこともある。やるよっ!。叩くよっ!」と自分に言い聞かせて開始。ところが、全く反応がない。2時間かけてトンネルまで叩き続けたのに、ショートバイトもない。追尾もない。エビもない。何も無かった。「これは、ちょっと異常過ぎる。この湖面ではあっても、あり得ない」と感じた。
「どうする?」と考え「ニナルの手前のワンドを叩く」と決めた。ここは、今年に入って2回、ほぼべた凪でも数尾のヒットがあった。午前11時半、これまで反応が集中した30m程度を叩いた。湖面は、支寒内より、ましだった。水温8.9℃。「このワンドでこの波があれば十分」と思えた。しかし、何もない。「マジッ?」という印象。そこで、ワンド全体を、2時間かけて等間隔で全部叩いた。しかし何もなかった。「アッパレ」と苦笑いするしかない無反応だった。

ここで「今日の月齢11は、フローティングミノーの釣りと相性が悪いかもしれない...」という疑問が生まれた。それならそれで、とことん、無反応を確認する必要がある。となると「波がある場所を探して、そこで数時間叩いて、完全な無反応を確認する必要がある」と判断。
車で、国道276号線を走り、所々で停車して湖面を見て回ったが「この波なら十分!」と思える場所がなかった。アメダスを見ると、天気予報とは正反対の「南東風」が吹き始めていた。「これなら丸駒が向い風になる」と判断し、このエリアに賭けることにした。波はあまり強くない。しかし、何とか食わせられそうな波だった。午後2時過ぎに開始。

開始1時間後「そろそろピックアップ」というタイミングの、岸から3〜4mの所で、いきなり「ドボンッ!」と、 凄い音の水柱が立ち、「はっ?。何これっ?」と思って見ていたら、ロッドが絞り込まれた。61cmのブラウントラウトだった(15:21)。


乗ったのは、三角印の場所。水深は20〜30cm。「こんな事が日中に起こるんだ...」と、初めて経験する乗り方に驚いた。夜釣りのトップウォーターへの反応のようだった。

さらに約1時間後、ゆっくり重みが乗り、ドラグからジリジリとラインが引き出された。久しぶりの重量感だった。「やったよ!。1年半ぶりの80cm台の引き方だよっ!」と喜んだ。ゆっくりと、やり取りし、ネットに入れた。入れた瞬間、70cmのフレームから、尾っぽが20cm近くはみ出している。「間違いない!。80cm台半ばはある」。ところが、ネットを持ち上げる瞬間、激しく暴れ出し、フックが折れ、ネットから飛び出し、逃げられてしまった...。茫然自失。
「ネットに入れた魚に逃げられる馬鹿が、どこの世界におっとや!。馬鹿か?貴様は!」と、怒りで一杯になった。
原因は簡単だった。今年、トレブルフックの付いたフローティングミノーを使う機会が増え、ラバーネットの必要性を感じていた。しかし「これだよ!これっ!」と思える製品が無かった。結局、ウォーターランドのメータースッポリネットという製品を購入し、ネットを外して、シーバス用のフレームに付けていた。しかし、このメータースッポリネットが、あまりにも浅かった。80cm台半ばになると、全くスッポリ入らない。逃げ出された瞬間、頭も尾っぽも5〜10cmずつ、はみ出していた。おまけに、フレームの付け根が、魚の重みと激しい暴れ方で、ひん曲がってしまった。このラバーネットが届いた時「これで、本当に80cmが入るのか?」と不安に感じたが、まさしく、不安通りの結果となってしまった。
頭を冷やせば、このランディングネットなら、ネットの操作を第三者に任せない限り、起こっても当たり前のことが、起こっただけだった...。「マーフィーの法則は正しかった」と思い知らされた。完全に自業自得。
これで完全に腹が立ち「絶対にもう1尾、獲ってやる」と躍起になり、叩ける所を全て叩いた。しかし、駄目だった。3回反応があり、1回は首振りで外れた。重みから60cmあるかないか程度。ネットに収められたのは、40cmちょっとと50cm前後の2尾。


午後6時半、叩く場所が無くなり、終了。
今日学んだことは2つ。1つは、当たり前のことだが、波だった。今日は、波が弱い場所では何の反応もなかった。ある程度の波がある場所を探せば、反応があった。この日の丸駒は「波が強めになったり、弱くなったり」を繰り返した。80cm台が乗ったのは、ちょうど、この日一番に波が強くなったタイミングだった。丸駒は、4〜5年前まで散々通い込んだエリアだった。ブラウントラウトが着きやすい場所は把握しているつもりだった。しかし、この魚が乗ったのは、これまで全く反応を得られなかった場所だった。「結局、波が強くなれば、どこにだってチャンスはある」と感じた。もう1つ学んだことは、ランディングネットの重要性。単独釣行の場合、念には念を入れた製品の選択と購入が、絶対に必要。

天気図は日本気象協会(http://www.tenki.jp/guide/chart/)を引用。
2018年05月23日
モンスター
1つ前の書き込みにコメントして下さった、yasuさんから、92cmのブラウントラウトの写真を送っていただきました。素晴らしい1尾ですね。羨ましい限りです。こんなに晴れた日に、こんなサイズを掛けたら「どんなに楽しいだろうか?」と、若干、嫉妬を感じてしまうモンスターです。本当に、おめでとうございます。そして、貴重な写真を提供して頂いたこと、yasuさん、本当にありがとうございます。支笏湖で釣りをする、私も含め、沢山の方にとって、この湖で釣りをする動機になり、励みになる、貴重な写真です。ありがとうございます。


2018年05月23日
モンスター
今年の春は、80cm台や90cmのニュースで湧いている支笏湖ですが、私もモンスターの捕獲を目撃しました。本人の了承を得て、写真を撮らせてもらいました。これを載せておきます。96cmのブラウントラウトです。凄い迫力の魚体でした。羨ましい限りです。おめでとうございます!。




2018年05月23日
支笏湖2018年5月20日
方法:岸からの釣り
月齢:5
気温:日平均13.7℃ (7.7~19.1℃)
水温:4.7℃ (4.4〜5.1℃)
時間:5時間 (午前4時〜午前9時)
反応:2回
釣果:0尾
この日は午前中だけ時間がとれたので、日の出から開始。今年、まだ叩いていないモーラップから千歳川アウトレットまでを叩いた。モーラップキャンプ場から開始した。波は十分過ぎる強さがあった。

ところが、アメマスばかりが反応してくる。30cm弱程度のサイズが中心だった。この日は結局、アメマス8尾で終わってしまった。


ブラウントラウトの反応は2回だけだった。いずれも、ブレイクが岸から15m程度の場所で、岸から5m程度の、かなり浅いとこころで乗った。食いが浅かったようで、いずれも数秒で抜けてしまった。重みから、どちらも40cm台。まともなサイズと思えるブラウントラウトの反応は無かった。
午前9時、最初の水中遊覧船がやってきたところで終了。この日は快晴で、モーラップまで散歩気分で景色を楽しみながら、水温をコンスタントに測っていった。

水温が低いのに驚いた。平均で4.7℃。5℃に達していない。4.4℃の場所もあった。昨日のモーラップ〜大沢橋は5.8℃から6.4℃だったので、1℃以上低かった。このエリアも、ニナル河口からフレナイ河口までの範囲と同様に、水温の上昇が遅れるエリアのようだった。
今年は5月もコンスタントに通っているが、ブラウントラウトの反応が良い日と、悪い日の落差が大きいことに驚いた。しかも、波があるから良いとも限らず、波がないから悪いとも限らない。釣果は、その日のブラウントラウトの気まぐれに翻弄される。この日の渋さも、水温が低いエリアだったことが原因なのか?、さっぱり分からない。もしかしたら、この前日や翌日だったらよく釣れたかもしれない。この時期の経験が少ないため、そうした判断が全くきかない。「この先、何年も通い込まないと、何一つ見えてこないだろうな...」と強く感じた。「見えてくるまでは、釣れようが釣れなかろうが、通い続けるしかない」と、自分に言い聞かせるしかなかった。

天気図は日本気象協会(http://www.tenki.jp/guide/chart/)を引用。
月齢:5
気温:日平均13.7℃ (7.7~19.1℃)
水温:4.7℃ (4.4〜5.1℃)
時間:5時間 (午前4時〜午前9時)
反応:2回
釣果:0尾
この日は午前中だけ時間がとれたので、日の出から開始。今年、まだ叩いていないモーラップから千歳川アウトレットまでを叩いた。モーラップキャンプ場から開始した。波は十分過ぎる強さがあった。

ところが、アメマスばかりが反応してくる。30cm弱程度のサイズが中心だった。この日は結局、アメマス8尾で終わってしまった。


ブラウントラウトの反応は2回だけだった。いずれも、ブレイクが岸から15m程度の場所で、岸から5m程度の、かなり浅いとこころで乗った。食いが浅かったようで、いずれも数秒で抜けてしまった。重みから、どちらも40cm台。まともなサイズと思えるブラウントラウトの反応は無かった。
午前9時、最初の水中遊覧船がやってきたところで終了。この日は快晴で、モーラップまで散歩気分で景色を楽しみながら、水温をコンスタントに測っていった。

水温が低いのに驚いた。平均で4.7℃。5℃に達していない。4.4℃の場所もあった。昨日のモーラップ〜大沢橋は5.8℃から6.4℃だったので、1℃以上低かった。このエリアも、ニナル河口からフレナイ河口までの範囲と同様に、水温の上昇が遅れるエリアのようだった。
今年は5月もコンスタントに通っているが、ブラウントラウトの反応が良い日と、悪い日の落差が大きいことに驚いた。しかも、波があるから良いとも限らず、波がないから悪いとも限らない。釣果は、その日のブラウントラウトの気まぐれに翻弄される。この日の渋さも、水温が低いエリアだったことが原因なのか?、さっぱり分からない。もしかしたら、この前日や翌日だったらよく釣れたかもしれない。この時期の経験が少ないため、そうした判断が全くきかない。「この先、何年も通い込まないと、何一つ見えてこないだろうな...」と強く感じた。「見えてくるまでは、釣れようが釣れなかろうが、通い続けるしかない」と、自分に言い聞かせるしかなかった。

天気図は日本気象協会(http://www.tenki.jp/guide/chart/)を引用。
2018年05月20日
支笏湖2018年5月19日
方法:岸からの釣り
月齢:4
気温:日平均7.6℃ (4.6~11.6℃)
水温:6.0℃ (5.8〜6.4℃)
時間:3時間 (午後1時〜午後3時半)
反応:4回
釣果:1尾
この数週間、反応の数は多いが、フッキングするサイズが小さい。時折「ガンッ」と重量感のあるショートバイトがあるので、良いサイズが岸際にいるのは間違いない。しかしショートバイトで終わる。明らかに、4月よりミノーが見切られている。
「ショートバイトと向き合わないといけない」と、痛感してきた。最初に思いつくのはフックだった。
自分は、ミノーのフックを、メーカーが出荷した時に付いているフックから、一切変更しない。過去に、これをして、効果的なアクションが消え「凄く釣れるミノー」が「全く見向きもされないミノー」に激変したことを経験している。それ以来、メーカーが指定したフックしか使わないようにしている。
過去にブラウントラウトのショートバイトを何度も目撃した経験から、ショートバイトは「ミノーを丸飲みするつもりで、ミノーに直進してきたブラウントラウトが、ミノーに襲いかかる直前に、ミノーを餌でないと見抜く現象」と考えるようになった。
ショートバイト対策は、ミノーに至近距離まで近づいたブラウントラウトが、ミノーを偽物と見破るきっかけを、1つでも減らすことだと感じていた。
今、マイブームになっているフローティングミノーの場合、試している多くのミノーは、トレブルフックが3個ついている。トラウト目線で見ると、フックの存在感が凄い。ミノー本体に匹敵している。3つのトレブルフックは、あたかも、トラウトに対し「俺は尖ったフックだぞっ!。ミノー本体に近づかせねぇぞっ!。このミノーは俺達フックが守ってるぞっ!。近づくんじゃねぇぞっ!。痛い目に会わせるぞっ!。」と威嚇し、トラウトからミノー本体を守る、防御壁の役目を果たしているように見える。この、存在感のある威嚇の効果は、ミノーを丸飲みしようとしたトラウトを意気消沈させ、ショートバイトの大きな原因になるかもしれない。

そこで、思い切り、フックを減らしてみることにした。テールに、シングルフックを1個付けるだけにした。この数ヶ月の50cm以上のブラウントラウトのヒットでは、フックが刺さったのは、下顎の先端付近だけだった。そこで、フックの先端が下になるように、シングルフックを1個だけにした。ブラウントラウトを獲るためなら、このフック1個で十分と判断した。

フックの存在感は、消えてはいない。しかし、かなり減ったはず。

これを試すと「どうなるか?」が、気になった。当然「ショートバイトがヒットになり、ヒットは丸飲みになって欲しい」と期待した。アクションの変化による負の影響が気になるが、これは湖岸で投げ続けて、確かめるしかない。
この日は、午後に時間をとれたので、3時間だけ叩いてきた。午後1時開始。国道を簡単に降りれて、すぐに釣りを始められる場所、3カ所を1時間ずつ叩いた。まずアクションを観察した。ミノーのアクションは、ウォブリングが極端に強くなり、バタバタ泳ぐクランクベイト風に変わっていた。ここで強い不安を覚えた。
まず支笏小橋からモーラップキャンプ場までの範囲。水温は6.4℃と高め。天気は曇りで、波は申し分ない条件だった。

ここはアメマスだらけだった。

25cmから30cm程度のアメマスを5本掛けた合間に、1回、ゴンッと、力強く、重量感のあるショートバイトがあった。「フックを減らしても、見切られるものは見切られる。結局、ショートバイトはショートバイト...」と、ガッカリとした。どうやら、ブラウントラウトがミノーを見切る原因として、フックはさほど重要ではないらしい。
次いで、樽前橋から紋別橋の区間。水温は5.9℃。ここではエビが1回だけだった。
最後に、大沢橋。水温は5.8℃。開始10分後、ミノーの背後に70cm近いブラウントラウトが付いた。しかしそのまま、ゆったりと帰ってしまった。その後「ゴンッ」とか「ガツンッ」という、重量感のあるショートバイトが2回。やっぱり見切られている。「トレブルフックのフル装備」でも「シングルフック1個だけ」でも、ロッドを握る手に感じる感触は全く同じだった。「トレブル vs. シングル」や「フック3個 vs. フック1個」の違いは、印象として、ショートバイトに何の影響も与えてない。
その後、ようやく、ゆっくり重みが乗って、55cmのブラウントラウト (15:40)。

「ヒットする時は、せめて、口先ではなく、口の奥でフッキングして欲しい」と期待していたが、相変わらず口先へのフッキングだった。フックをシングル1個にしたからといって、ミノーを丸飲みする訳ではなかった。これにもガッカリしてしまった。
たった3時間の釣行だった。「トレブルのフル装備」と「シングル1個」を、客観的に比較できたわけではない。しかし、印象として「トレブル3個を、シングル1個にしたからといって、特に大きな変化はない」としか感じられなかった。

天気図は日本気象協会(http://www.tenki.jp/guide/chart/)を引用。
月齢:4
気温:日平均7.6℃ (4.6~11.6℃)
水温:6.0℃ (5.8〜6.4℃)
時間:3時間 (午後1時〜午後3時半)
反応:4回
釣果:1尾
この数週間、反応の数は多いが、フッキングするサイズが小さい。時折「ガンッ」と重量感のあるショートバイトがあるので、良いサイズが岸際にいるのは間違いない。しかしショートバイトで終わる。明らかに、4月よりミノーが見切られている。
「ショートバイトと向き合わないといけない」と、痛感してきた。最初に思いつくのはフックだった。
自分は、ミノーのフックを、メーカーが出荷した時に付いているフックから、一切変更しない。過去に、これをして、効果的なアクションが消え「凄く釣れるミノー」が「全く見向きもされないミノー」に激変したことを経験している。それ以来、メーカーが指定したフックしか使わないようにしている。
過去にブラウントラウトのショートバイトを何度も目撃した経験から、ショートバイトは「ミノーを丸飲みするつもりで、ミノーに直進してきたブラウントラウトが、ミノーに襲いかかる直前に、ミノーを餌でないと見抜く現象」と考えるようになった。
ショートバイト対策は、ミノーに至近距離まで近づいたブラウントラウトが、ミノーを偽物と見破るきっかけを、1つでも減らすことだと感じていた。
今、マイブームになっているフローティングミノーの場合、試している多くのミノーは、トレブルフックが3個ついている。トラウト目線で見ると、フックの存在感が凄い。ミノー本体に匹敵している。3つのトレブルフックは、あたかも、トラウトに対し「俺は尖ったフックだぞっ!。ミノー本体に近づかせねぇぞっ!。このミノーは俺達フックが守ってるぞっ!。近づくんじゃねぇぞっ!。痛い目に会わせるぞっ!。」と威嚇し、トラウトからミノー本体を守る、防御壁の役目を果たしているように見える。この、存在感のある威嚇の効果は、ミノーを丸飲みしようとしたトラウトを意気消沈させ、ショートバイトの大きな原因になるかもしれない。


そこで、思い切り、フックを減らしてみることにした。テールに、シングルフックを1個付けるだけにした。この数ヶ月の50cm以上のブラウントラウトのヒットでは、フックが刺さったのは、下顎の先端付近だけだった。そこで、フックの先端が下になるように、シングルフックを1個だけにした。ブラウントラウトを獲るためなら、このフック1個で十分と判断した。

フックの存在感は、消えてはいない。しかし、かなり減ったはず。

これを試すと「どうなるか?」が、気になった。当然「ショートバイトがヒットになり、ヒットは丸飲みになって欲しい」と期待した。アクションの変化による負の影響が気になるが、これは湖岸で投げ続けて、確かめるしかない。
この日は、午後に時間をとれたので、3時間だけ叩いてきた。午後1時開始。国道を簡単に降りれて、すぐに釣りを始められる場所、3カ所を1時間ずつ叩いた。まずアクションを観察した。ミノーのアクションは、ウォブリングが極端に強くなり、バタバタ泳ぐクランクベイト風に変わっていた。ここで強い不安を覚えた。
まず支笏小橋からモーラップキャンプ場までの範囲。水温は6.4℃と高め。天気は曇りで、波は申し分ない条件だった。

ここはアメマスだらけだった。

25cmから30cm程度のアメマスを5本掛けた合間に、1回、ゴンッと、力強く、重量感のあるショートバイトがあった。「フックを減らしても、見切られるものは見切られる。結局、ショートバイトはショートバイト...」と、ガッカリとした。どうやら、ブラウントラウトがミノーを見切る原因として、フックはさほど重要ではないらしい。
次いで、樽前橋から紋別橋の区間。水温は5.9℃。ここではエビが1回だけだった。
最後に、大沢橋。水温は5.8℃。開始10分後、ミノーの背後に70cm近いブラウントラウトが付いた。しかしそのまま、ゆったりと帰ってしまった。その後「ゴンッ」とか「ガツンッ」という、重量感のあるショートバイトが2回。やっぱり見切られている。「トレブルフックのフル装備」でも「シングルフック1個だけ」でも、ロッドを握る手に感じる感触は全く同じだった。「トレブル vs. シングル」や「フック3個 vs. フック1個」の違いは、印象として、ショートバイトに何の影響も与えてない。
その後、ようやく、ゆっくり重みが乗って、55cmのブラウントラウト (15:40)。

「ヒットする時は、せめて、口先ではなく、口の奥でフッキングして欲しい」と期待していたが、相変わらず口先へのフッキングだった。フックをシングル1個にしたからといって、ミノーを丸飲みする訳ではなかった。これにもガッカリしてしまった。
たった3時間の釣行だった。「トレブルのフル装備」と「シングル1個」を、客観的に比較できたわけではない。しかし、印象として「トレブル3個を、シングル1個にしたからといって、特に大きな変化はない」としか感じられなかった。

天気図は日本気象協会(http://www.tenki.jp/guide/chart/)を引用。
2018年05月16日
支笏湖2018年5月13日
方法:岸からの釣り
月齢:27
気温:日平均10.1℃ (4.8~14.7℃)
水温:4.6℃ (4.3〜4.9℃)
時間:9時間 (午前4時〜午後5時半)
反応:7回
釣果:5尾
この日は、まず「2日前の群れがまだいるのか?」それとも「消え失せたのか?」だった。早起きしてしまい、そのまま札幌を出発。午前3時過ぎ、支笏湖トンネルに到着。夜釣りの車が6台。湖岸に降りると、叩きたい周辺を含め、あちこちでヘッドランプ。「こりゃ駄目だ」と断念。
午前4時過ぎ、ニナル手前のワンドで開始した。ほぼべた凪。しかし「あの活性が続いていれば、これでも十分に食わせられる」と、開始時点では自信満々だった。

ところが、全く反応が無かった。2時間、広範囲を叩いて、30cmに満たないブラウントラウトが2尾だけ (写真はなし)。ここで「活性の高いブラウントラウトの群れとの遭遇は、一期一会」と教訓を得た。そんなに都合の良い状況は「偶然、かつ、その日限り」。「あの時、もっと様々なルアーで叩いて、釣れるだけ釣っておくべきだった...」と後悔した。
この日は低気圧が接近中で、天気予報では強めの南風だった。しかし低気圧の勢力が弱く、べた凪の曇天で、時おり小雨。アメダスで弱い北西風が出ているのを確認し、国道276号線を東に向かい、波の出ているエリアを探したが、どこも駄目。波が足りない。
仕方ないので、旧有料道路で再開。水温4.3℃。

開始1投目で、しっかりコンッとショートバイトがあり、50cm台のブラウントラウトが反転する姿が見えた。「これはいける」と感じたが、2時間叩いても、ブラウントラウトの反応は続かなかった。相手をしてくれるのはアメマスだけ。

ここで、打つ手を完全に失ってしまった。「仕方ない、健康のために歩こう」と、美笛に戻り、林道を歩いてフレナイ河口まで行った。水温は4.9℃。「もしかしたら、予報通り南風が吹くかもしれない」と期待したが、湖面は穏やかだった。砂利浜を、初めて使う数種類のルアーで試し、クイッという、引っ張るようなショートバイトが1回だけだった。

午後2時過ぎ、南岸から、天気予報通り、最低限の波がやって来た。

ここで「ニナルまで叩きまくろう」と決心し、等間隔で叩きまくった。しかし、渋かった。ショートバイトが3回。いずれも、ブレイクが岸から5m程度の場所で、明確なコンッという間隔がロッドに伝わり、ルアーの位置で、反転して帰っていくブラウントラウトの姿が見えた。ミノーを丸飲みしてくれない。50cm前後が2尾、60cm前後が1尾。
「それでも叩き続けるしかないだろ」と自分に言い聞かせ、淡々と叩き続け、ようやくヒット。30cm台半ばのブラウントラウトだった(15:04)。釣りを開始して11時間。やっと30cmを超えた。「今日って、一体、何?」と愚痴るしかなかった。

その後、50cm (15:17) と30cm強 (16:25) を追加。


ここで、また湖面が穏やかになってしまった。

その後、1時間、何も起こらなかった。「波がなければ、何も起こらない」いつもの支笏湖に戻ってしまった。活性の高い群れとは遭遇できなかった。午後5時半、終了。

天気図は日本気象協会(http://www.tenki.jp/guide/chart/)を引用。
月齢:27
気温:日平均10.1℃ (4.8~14.7℃)
水温:4.6℃ (4.3〜4.9℃)
時間:9時間 (午前4時〜午後5時半)
反応:7回
釣果:5尾
この日は、まず「2日前の群れがまだいるのか?」それとも「消え失せたのか?」だった。早起きしてしまい、そのまま札幌を出発。午前3時過ぎ、支笏湖トンネルに到着。夜釣りの車が6台。湖岸に降りると、叩きたい周辺を含め、あちこちでヘッドランプ。「こりゃ駄目だ」と断念。
午前4時過ぎ、ニナル手前のワンドで開始した。ほぼべた凪。しかし「あの活性が続いていれば、これでも十分に食わせられる」と、開始時点では自信満々だった。

ところが、全く反応が無かった。2時間、広範囲を叩いて、30cmに満たないブラウントラウトが2尾だけ (写真はなし)。ここで「活性の高いブラウントラウトの群れとの遭遇は、一期一会」と教訓を得た。そんなに都合の良い状況は「偶然、かつ、その日限り」。「あの時、もっと様々なルアーで叩いて、釣れるだけ釣っておくべきだった...」と後悔した。
この日は低気圧が接近中で、天気予報では強めの南風だった。しかし低気圧の勢力が弱く、べた凪の曇天で、時おり小雨。アメダスで弱い北西風が出ているのを確認し、国道276号線を東に向かい、波の出ているエリアを探したが、どこも駄目。波が足りない。
仕方ないので、旧有料道路で再開。水温4.3℃。

開始1投目で、しっかりコンッとショートバイトがあり、50cm台のブラウントラウトが反転する姿が見えた。「これはいける」と感じたが、2時間叩いても、ブラウントラウトの反応は続かなかった。相手をしてくれるのはアメマスだけ。

ここで、打つ手を完全に失ってしまった。「仕方ない、健康のために歩こう」と、美笛に戻り、林道を歩いてフレナイ河口まで行った。水温は4.9℃。「もしかしたら、予報通り南風が吹くかもしれない」と期待したが、湖面は穏やかだった。砂利浜を、初めて使う数種類のルアーで試し、クイッという、引っ張るようなショートバイトが1回だけだった。

午後2時過ぎ、南岸から、天気予報通り、最低限の波がやって来た。

ここで「ニナルまで叩きまくろう」と決心し、等間隔で叩きまくった。しかし、渋かった。ショートバイトが3回。いずれも、ブレイクが岸から5m程度の場所で、明確なコンッという間隔がロッドに伝わり、ルアーの位置で、反転して帰っていくブラウントラウトの姿が見えた。ミノーを丸飲みしてくれない。50cm前後が2尾、60cm前後が1尾。
「それでも叩き続けるしかないだろ」と自分に言い聞かせ、淡々と叩き続け、ようやくヒット。30cm台半ばのブラウントラウトだった(15:04)。釣りを開始して11時間。やっと30cmを超えた。「今日って、一体、何?」と愚痴るしかなかった。

その後、50cm (15:17) と30cm強 (16:25) を追加。


ここで、また湖面が穏やかになってしまった。

その後、1時間、何も起こらなかった。「波がなければ、何も起こらない」いつもの支笏湖に戻ってしまった。活性の高い群れとは遭遇できなかった。午後5時半、終了。

天気図は日本気象協会(http://www.tenki.jp/guide/chart/)を引用。
2018年05月13日
支笏湖2018年5月11日
■脚注■バタバタしており、更新が遅れています。これは金曜日(5/11)の釣行記録です。今日も行って来たのですが、その分の更新は数日中に行う予定です。
方法:岸からの釣り
月齢:25
気温:日平均10.1℃ (4.8~14.7℃)
水温:5.9℃ (4.9〜7.3℃)
時間:9時間 (午前7時〜午後6時)
反応:17回
釣果:7尾
この日は南風の予報だった。経験から、南風の予報は外れる場合が多く、大半の場合、西風が吹く。この日は、もし南風なら西岸でトップウォーターの修行。西風なら、南岸のまだ叩いていないエリアで、大きめで重ためのフローティングミノーの釣り。そう決めていた。この釣りを、2週間もサボっている。
西風だったので、午前7時過ぎ、美笛キャンプ場入口の砂浜で開始。天気は晴れ。この日は、支笏湖トンネルまでの範囲を叩くことにした。昔、散々通い込んだ懐かしいエリア。美笛の船着き場から、北北西の横風が強く吹き込んでいて、波も抜群だった。

開始5投目に40cm強のブラウントラウト (7:19)。ここで水温を測ると4.9℃。

その後、88km地点までの間に、クイッと引っ張るショートバイトが1回。ここで「この北西風なら、ニナルもチェックしておくべき」と感じ、午前9時頃にニナルに移動。ところが、ここは別世界のような、穏やかな湖面だった。

「馬鹿だった」と後悔したが「来た以上、叩くだけ叩こう」と、叩いてみた。まずニナル河口周辺の300m程度の範囲。1回、ゴンッと手元に強い衝撃が伝わった。しかし、乗らなかった。「この波じゃ駄目。早く戻ろう」と痛感したが、念のため、ワンドも叩いてみた。投げ続けていると、ワンドの中の、ほんの20m程度の範囲で、沢山の反応に遭遇した。
1回目。いきなり重みが乗り、そのまま抜けた。2回目。クイッと引っ張るショートバイト。3回目。ゆっくり重みが乗った。52cmのブラウントラウト (9:57)。

4回目が衝撃的だった。ブレイクが岸から15m程度の場所で、岸から5m、水深30〜40cmで、いきなり重みが乗り、60cm半ば程度のブラウントラウトが、全身を使って激しく首振りをしていた。5〜6回目で抜けてしまった。「この波で、こんな浅い場所で、このサイズが乗るか?」と、呆然としてしまった光景だった。5回目。重みが乗って、直後に外れた。これら全部の反応が、たった8投で起きた。使ったのは12〜13cmのリップの付いたミノー。引き抵抗も大きく、こんなべた凪直前の湖面で反応するはずもなかった。
そして、さらに等間隔で叩き続けると、完全に無反応になった。
このワンドでこれだけ反応が多いのは、初めての経験だった。水温を測ると6.1℃。それなりに高い。「ニナル河口の向こう側の水温は?」と気になり、ニナル河口に戻った。5.3℃。数百mで0.8℃上昇していた。ここは、美笛の遠浅に隣接した、暖かいエリアとなっているようだった。「弱いさざ波でも平気でルアーに反応する高活性の群れが、この時期、このワンドに入ることがあるんだ...」と、ただただ驚いた。
このワンドは美笛の北端なので「それなら、美笛の南端も、同じことがあり得る」と判断。そこで正午前頃に美笛の船着き場に移動した。水温は5.6℃。そのまま美笛キャンプ場まで行くと、水温7.3℃。「これなら、この範囲にも、同じような、安直にルアーに反応する連中がいるはず」と期待した。しかも、波も悪くなかった。

2時間かけて、この範囲を叩いた。しかし、何一つ反応は無かった。「そんなに甘くはないか...」と、見込みの甘さを反省。
午後2時頃に88km地点に戻った。すでに、朝と比べると、波が弱くなっていた。しかし「さっきのこともある。続けるよ。トンネルまで叩くよ。」と自分に言い聞かせて再開した。

開始10分程度で40cm強 (14:06)。

その後、グイッと引っ張るような、重量感のあるショートバイトが2回。さすがに、快晴の真っ昼間のさざ波「さすがに、このサイズは騙せない」と実感。さらに叩いていると、やっと重みが乗り、54cmのブラウントラウト (15:24)。

ここからが、再度、衝撃的だった。このヒットの2投後、グンッと引っ張るように重みが乗り、その直後に外れた。さらに5m程度移動した1投に重みがのり、首振り1回で抜けた。さらに5mで、今度はグイッと引っ張るショートバイト。
たった20m程度の範囲で、たった5投で、4尾が反応してきた。重みから全て50cm前後。デカいと思える反応はなかった。しかし、驚くしかない反応だった。というのも、この時すでに、湖面はべた凪一歩手前の状態だった。太陽が背後の山に隠れてローライトになっているが、依然、空は快晴だった。それでも果敢にルアーに反応してきた。

「間違いない。ところどころ、局所的だが、メチャクチャ活性のブラウントラウトの群れが、ポツリポツリといる」と確信できる結果だった。「これが5月上旬の支笏湖なんだ」と、身をもって感じることができた。過去に、GW前後の爆釣の話を何度か聞いたことがある。今日はサイズも数も限られ「爆釣」にはほど遠いが、これで「あの信じ難い爆釣の話は、この現象の延長線だったんだ」と、やっと実感できた。
その後、30cm台半ばを2本追加し


そろそろ「疲れた」と感じたところで、ガンッと引ったくるような、重量感のあるショートバイトがあった。その5投程度後に、ゆっくり重みが乗った。42cmのブラウントラウト (15:53)。

この時点で、釣りを始めて11時間。実釣9時間。「なんとか1本、60cm台が欲しい」と叩き続けてきたが、これで断念。午後6時に終了。
この日は、勉強になった1日だった。ここまで湖面が穏やかでも、ブラウントラウトのルアーへの反応が良いことがある。これを体験できた。いつもなら「この湖面なら叩くだけ無駄」と判断して、そのエリアを切り捨てる状況で、馬鹿正直に叩き続けて得られた教訓だった。
この日、驚いたのは、特に2点。
第一点。局所的だし、数は多くないが、所々、とんでもなく活性の高いブラウントラウトの群れがいる。快晴の真っ昼間でも、べた凪に近い湖面でも、果敢にミノーに反応してくる。
第二点。今回10〜15gの大きめのフローティングミノーを使った。3月からこれを続けてきた。これまでは、体当たりされて、エビになって水面から飛び出すだけだった。明らかに、テリトリーを脅かす侵入者にしか見られていなかった。この釣りは、GW前までの2ヶ月間、本当につまらなかった。ショートバイトが1回も無かった。しかし今回は、明らかに口を使ったショートバイトが何度もあった。口を使っている以上、侵入者から餌に変わりつつある。
反省が1つ。最近はリップの付いたフローティングミノーがマイブームで、それしか使わなかった。しかし、べた凪近い条件であったことから「シンキングペンシル等の、ただ巻きで使えて、波動の小さいルアーを使えば、数もサイズも、もっと上がったはずだった」と、帰ってから気付いた。馬鹿だった。
■情報提供のお願い■ 今回、私は異常な位に、ルアーへの活性の高いブラウントラウトの、2つの群れと遭遇しました。もし、この数週間のうちに、私同様に「こんなに反応するのは異常」とか「こんなに釣れたことは滅多にない」という経験をされた方がいましたら、教えて頂けないでしょうか?。基本的に、知りたいのは「日付」です。この情報があれば「狭い範囲の日数に集中する現象なのか?」それとも「数週間という長めのスパンの中で、散発的かつ偶発的に起こる現象なのか?」が分かります。もし可能であれば、ルアーのジャンルの別(ミノー、シンキングペンシル、スプーン、メタルジグ)やエリアの別(東岸、西岸、南岸、北岸)の情報を教えて頂けると、さらに何かのヒントになるかもしれません。この現象のパターンが分かれば、どなたにとっても、有益な情報になると思います。

天気図は日本気象協会(http://www.tenki.jp/guide/chart/)を引用。
方法:岸からの釣り
月齢:25
気温:日平均10.1℃ (4.8~14.7℃)
水温:5.9℃ (4.9〜7.3℃)
時間:9時間 (午前7時〜午後6時)
反応:17回
釣果:7尾
この日は南風の予報だった。経験から、南風の予報は外れる場合が多く、大半の場合、西風が吹く。この日は、もし南風なら西岸でトップウォーターの修行。西風なら、南岸のまだ叩いていないエリアで、大きめで重ためのフローティングミノーの釣り。そう決めていた。この釣りを、2週間もサボっている。
西風だったので、午前7時過ぎ、美笛キャンプ場入口の砂浜で開始。天気は晴れ。この日は、支笏湖トンネルまでの範囲を叩くことにした。昔、散々通い込んだ懐かしいエリア。美笛の船着き場から、北北西の横風が強く吹き込んでいて、波も抜群だった。

開始5投目に40cm強のブラウントラウト (7:19)。ここで水温を測ると4.9℃。

その後、88km地点までの間に、クイッと引っ張るショートバイトが1回。ここで「この北西風なら、ニナルもチェックしておくべき」と感じ、午前9時頃にニナルに移動。ところが、ここは別世界のような、穏やかな湖面だった。

「馬鹿だった」と後悔したが「来た以上、叩くだけ叩こう」と、叩いてみた。まずニナル河口周辺の300m程度の範囲。1回、ゴンッと手元に強い衝撃が伝わった。しかし、乗らなかった。「この波じゃ駄目。早く戻ろう」と痛感したが、念のため、ワンドも叩いてみた。投げ続けていると、ワンドの中の、ほんの20m程度の範囲で、沢山の反応に遭遇した。
1回目。いきなり重みが乗り、そのまま抜けた。2回目。クイッと引っ張るショートバイト。3回目。ゆっくり重みが乗った。52cmのブラウントラウト (9:57)。

4回目が衝撃的だった。ブレイクが岸から15m程度の場所で、岸から5m、水深30〜40cmで、いきなり重みが乗り、60cm半ば程度のブラウントラウトが、全身を使って激しく首振りをしていた。5〜6回目で抜けてしまった。「この波で、こんな浅い場所で、このサイズが乗るか?」と、呆然としてしまった光景だった。5回目。重みが乗って、直後に外れた。これら全部の反応が、たった8投で起きた。使ったのは12〜13cmのリップの付いたミノー。引き抵抗も大きく、こんなべた凪直前の湖面で反応するはずもなかった。
そして、さらに等間隔で叩き続けると、完全に無反応になった。
このワンドでこれだけ反応が多いのは、初めての経験だった。水温を測ると6.1℃。それなりに高い。「ニナル河口の向こう側の水温は?」と気になり、ニナル河口に戻った。5.3℃。数百mで0.8℃上昇していた。ここは、美笛の遠浅に隣接した、暖かいエリアとなっているようだった。「弱いさざ波でも平気でルアーに反応する高活性の群れが、この時期、このワンドに入ることがあるんだ...」と、ただただ驚いた。
このワンドは美笛の北端なので「それなら、美笛の南端も、同じことがあり得る」と判断。そこで正午前頃に美笛の船着き場に移動した。水温は5.6℃。そのまま美笛キャンプ場まで行くと、水温7.3℃。「これなら、この範囲にも、同じような、安直にルアーに反応する連中がいるはず」と期待した。しかも、波も悪くなかった。

2時間かけて、この範囲を叩いた。しかし、何一つ反応は無かった。「そんなに甘くはないか...」と、見込みの甘さを反省。
午後2時頃に88km地点に戻った。すでに、朝と比べると、波が弱くなっていた。しかし「さっきのこともある。続けるよ。トンネルまで叩くよ。」と自分に言い聞かせて再開した。

開始10分程度で40cm強 (14:06)。

その後、グイッと引っ張るような、重量感のあるショートバイトが2回。さすがに、快晴の真っ昼間のさざ波「さすがに、このサイズは騙せない」と実感。さらに叩いていると、やっと重みが乗り、54cmのブラウントラウト (15:24)。

ここからが、再度、衝撃的だった。このヒットの2投後、グンッと引っ張るように重みが乗り、その直後に外れた。さらに5m程度移動した1投に重みがのり、首振り1回で抜けた。さらに5mで、今度はグイッと引っ張るショートバイト。
たった20m程度の範囲で、たった5投で、4尾が反応してきた。重みから全て50cm前後。デカいと思える反応はなかった。しかし、驚くしかない反応だった。というのも、この時すでに、湖面はべた凪一歩手前の状態だった。太陽が背後の山に隠れてローライトになっているが、依然、空は快晴だった。それでも果敢にルアーに反応してきた。

「間違いない。ところどころ、局所的だが、メチャクチャ活性のブラウントラウトの群れが、ポツリポツリといる」と確信できる結果だった。「これが5月上旬の支笏湖なんだ」と、身をもって感じることができた。過去に、GW前後の爆釣の話を何度か聞いたことがある。今日はサイズも数も限られ「爆釣」にはほど遠いが、これで「あの信じ難い爆釣の話は、この現象の延長線だったんだ」と、やっと実感できた。
その後、30cm台半ばを2本追加し


そろそろ「疲れた」と感じたところで、ガンッと引ったくるような、重量感のあるショートバイトがあった。その5投程度後に、ゆっくり重みが乗った。42cmのブラウントラウト (15:53)。

この時点で、釣りを始めて11時間。実釣9時間。「なんとか1本、60cm台が欲しい」と叩き続けてきたが、これで断念。午後6時に終了。
この日は、勉強になった1日だった。ここまで湖面が穏やかでも、ブラウントラウトのルアーへの反応が良いことがある。これを体験できた。いつもなら「この湖面なら叩くだけ無駄」と判断して、そのエリアを切り捨てる状況で、馬鹿正直に叩き続けて得られた教訓だった。
この日、驚いたのは、特に2点。
第一点。局所的だし、数は多くないが、所々、とんでもなく活性の高いブラウントラウトの群れがいる。快晴の真っ昼間でも、べた凪に近い湖面でも、果敢にミノーに反応してくる。
第二点。今回10〜15gの大きめのフローティングミノーを使った。3月からこれを続けてきた。これまでは、体当たりされて、エビになって水面から飛び出すだけだった。明らかに、テリトリーを脅かす侵入者にしか見られていなかった。この釣りは、GW前までの2ヶ月間、本当につまらなかった。ショートバイトが1回も無かった。しかし今回は、明らかに口を使ったショートバイトが何度もあった。口を使っている以上、侵入者から餌に変わりつつある。
反省が1つ。最近はリップの付いたフローティングミノーがマイブームで、それしか使わなかった。しかし、べた凪近い条件であったことから「シンキングペンシル等の、ただ巻きで使えて、波動の小さいルアーを使えば、数もサイズも、もっと上がったはずだった」と、帰ってから気付いた。馬鹿だった。
■情報提供のお願い■ 今回、私は異常な位に、ルアーへの活性の高いブラウントラウトの、2つの群れと遭遇しました。もし、この数週間のうちに、私同様に「こんなに反応するのは異常」とか「こんなに釣れたことは滅多にない」という経験をされた方がいましたら、教えて頂けないでしょうか?。基本的に、知りたいのは「日付」です。この情報があれば「狭い範囲の日数に集中する現象なのか?」それとも「数週間という長めのスパンの中で、散発的かつ偶発的に起こる現象なのか?」が分かります。もし可能であれば、ルアーのジャンルの別(ミノー、シンキングペンシル、スプーン、メタルジグ)やエリアの別(東岸、西岸、南岸、北岸)の情報を教えて頂けると、さらに何かのヒントになるかもしれません。この現象のパターンが分かれば、どなたにとっても、有益な情報になると思います。

天気図は日本気象協会(http://www.tenki.jp/guide/chart/)を引用。
2018年05月06日
春の湖の水温変化
久々に、陸水学の話題を書きます。春の湖についてです。日本の陸水学の教科書には載っていないデータで、春の湖の変化を分かりやすく教えてくれる内容があります。アメリカの五大湖の1つ、オンタリオ湖のデータです。(図はhttp://www. miseagrant. umich.edu /explore /about-the- great-lakes /lake-ontario/を引用、写真はhttps:/ /www.worldatlas. com/articles/ just-how-big- is-lake-ontario .htmlを引用)


冬期間は結氷する湖です。この点で、支笏湖とは異なっています。(写真はhttps:/ /www.worldatlas. com/articles/ just-how-big- is-lake-ontario .htmlを引用)

見てもらうのは、この湖の春の水温分布の変化です。まず、湖面の氷が解けた直後です。4月下旬のデータです。湖水は一様に2〜3℃です。支笏湖なら、3下旬〜4月中旬の、一様に4℃の湖水に対応すると見なせます。

オンタリオ湖の湖水に、春の訪れが明確に現れるのは5月初旬〜中旬です。岸近くで、水温が上昇し始めます。

岸近くで水温が上昇する理由は簡単です。シャローの存在です。太陽の光が、ボトムに届きます。底質が砂利だろうと砂だろうと岩だろうと、太陽の光は、このボトムを温めます。そこで、夜間でも、温まったボトムが「カイロ「もしくは「湯たんぽ」の役割を果たし、湖水を温めます。そこで、水深の浅いシャローから水温が上昇します。

現在の支笏湖は、この状態に入っていると思います。支笏湖を岸際から温める効果が高いのは、遠浅のシャローです。支笏湖なら、美笛、支寒内〜94km、大沢橋〜支笏小橋、支笏湖温泉街、旧有料道路の北側の砂浜〜ポロピナイの5カ所でしょう。現在、この5カ所が巨大な「カイロもしくは湯たんぽ」となり、支笏湖の岸近くの湖水を温めているはずです。
一方、ブレイクが岸から近過ぎて、シャローの「カイロもしくは湯たんぽ」の機能がほとんど働かないエリアもあります。典型は、ニナル河口〜フレナイ河口、それから、旧有料道路の第7覆道以南になります。例年、この2つのエリアは、水温の上昇が他のエリアより1〜3週間遅いです。
これから数週間もしくは1ヶ月の間は、ベイトにとってもトラウトにとっても、岸近くだけが、暖かくて居心地の良い場所になってきます。そして、岸際の水温が7℃前後になったところで、アメマスが大挙して岸際に押し寄せて来ます。その1〜2週間後には、ウグイが大挙して岸際に押し寄せてきます。5月の支笏湖は、魚もエビも生き物みんなが、暖かい岸際を求めてくると考えて、よいと思います。さらに、5月末になれば、ハルゼミが鳴き始めます。
オンタリオ湖に話を戻します。6月に入ると、岸際で温められた湖水が、徐々に沖に広がっていきます。暖かい水は軽いです。ゆっくりと、湖面を滑るように、沖に広がります。

そして、最終的に、湖面が暖かい表水層で覆われ、深水層と分離し、水温躍層の形成が完了します。

この時点で、トラウトの釣りはレイクトローリングやボートからのバーティカル・ジギングの独断場となります。このダイナミックな変化は、支笏湖では、多分6月〜7月上旬に起きているだろうと、考えています。
こうした湖の変化を意識しながら、釣れるルアーや操作法の変化を感じられるようになると、春から初夏の支笏湖は、もっと楽しくなると思います。私は仕事の都合上、このシーズンはなかなか釣行できませんでした。しかし、今年からは、春のシーズナルパターンを探していきたいと考えています。


冬期間は結氷する湖です。この点で、支笏湖とは異なっています。(写真はhttps:/ /www.worldatlas. com/articles/ just-how-big- is-lake-ontario .htmlを引用)

見てもらうのは、この湖の春の水温分布の変化です。まず、湖面の氷が解けた直後です。4月下旬のデータです。湖水は一様に2〜3℃です。支笏湖なら、3下旬〜4月中旬の、一様に4℃の湖水に対応すると見なせます。

オンタリオ湖の湖水に、春の訪れが明確に現れるのは5月初旬〜中旬です。岸近くで、水温が上昇し始めます。

岸近くで水温が上昇する理由は簡単です。シャローの存在です。太陽の光が、ボトムに届きます。底質が砂利だろうと砂だろうと岩だろうと、太陽の光は、このボトムを温めます。そこで、夜間でも、温まったボトムが「カイロ「もしくは「湯たんぽ」の役割を果たし、湖水を温めます。そこで、水深の浅いシャローから水温が上昇します。

現在の支笏湖は、この状態に入っていると思います。支笏湖を岸際から温める効果が高いのは、遠浅のシャローです。支笏湖なら、美笛、支寒内〜94km、大沢橋〜支笏小橋、支笏湖温泉街、旧有料道路の北側の砂浜〜ポロピナイの5カ所でしょう。現在、この5カ所が巨大な「カイロもしくは湯たんぽ」となり、支笏湖の岸近くの湖水を温めているはずです。
一方、ブレイクが岸から近過ぎて、シャローの「カイロもしくは湯たんぽ」の機能がほとんど働かないエリアもあります。典型は、ニナル河口〜フレナイ河口、それから、旧有料道路の第7覆道以南になります。例年、この2つのエリアは、水温の上昇が他のエリアより1〜3週間遅いです。
これから数週間もしくは1ヶ月の間は、ベイトにとってもトラウトにとっても、岸近くだけが、暖かくて居心地の良い場所になってきます。そして、岸際の水温が7℃前後になったところで、アメマスが大挙して岸際に押し寄せて来ます。その1〜2週間後には、ウグイが大挙して岸際に押し寄せてきます。5月の支笏湖は、魚もエビも生き物みんなが、暖かい岸際を求めてくると考えて、よいと思います。さらに、5月末になれば、ハルゼミが鳴き始めます。
オンタリオ湖に話を戻します。6月に入ると、岸際で温められた湖水が、徐々に沖に広がっていきます。暖かい水は軽いです。ゆっくりと、湖面を滑るように、沖に広がります。

そして、最終的に、湖面が暖かい表水層で覆われ、深水層と分離し、水温躍層の形成が完了します。

この時点で、トラウトの釣りはレイクトローリングやボートからのバーティカル・ジギングの独断場となります。このダイナミックな変化は、支笏湖では、多分6月〜7月上旬に起きているだろうと、考えています。
こうした湖の変化を意識しながら、釣れるルアーや操作法の変化を感じられるようになると、春から初夏の支笏湖は、もっと楽しくなると思います。私は仕事の都合上、このシーズンはなかなか釣行できませんでした。しかし、今年からは、春のシーズナルパターンを探していきたいと考えています。
2018年05月04日
支笏湖2018年5月3日
方法:岸からの釣り
月齢:17
気温:日平均9.1℃ (6.2~11.4℃)
水温:3.8℃ (3.7〜3.9℃)
時間:7時間半 (午前5時〜午後1時)
反応:9回
釣果:4尾
この日の目的は、先週に叩けなかったニナル河口〜フレナイ河口の2/3程度の範囲を、全部叩くことだった。
天候は小雨〜雨。南東から強めの波が来ている。「釣れないはずがない」と確信できる条件だった。先行者の要素を排除したいので、早起きして、午前5時過ぎに開始。水温は3.8℃(3.9, 3.7, 3.8, 3.9)。先週より0.3℃上昇したが、未だ、4.0℃以下。このエリアは、まだ早春を引きずっていて、春が来ていない。

先週に引き続き、小さめで軽めのミノーのトゥイッチ。開始4投目で、重みが乗った。ブレイクのショルダーより、かなり手前。岸から3〜4m、水深50cmに満たない所で、いきなりミノーの背後に現れ、その数秒後に乗った。食うことを、かなり躊躇している。しかし何とか丸飲みしてくれた。61cmの、腹が痩せたブラウントラウト (5:18)。


その30分後、岸から6〜7m、水深1m強程度のところで、ミノーの後ろに60cm前後のブラウントラウトがピタリと付いた。しかし、数秒後には反転して去って行った。「マジかっ?」と愕然とした。このミノーのこの反応は、初めてだった。
「やっぱり、このミノーも落ち目か」と感じた。これまでの経験から、「これは凄い!」とビックリしたミノーも、同じエリアで叩き続けると、数年後には全く釣れなくなってしまう。しかし一方で、気になる点があった。
この日は、15年以上前に買った、10gまで投げられる6.1ftのソリッドティップのバスロッドを使った。6.1ftと短く、トゥイッチのロッド操作がしやすい。ただし、ソリッド部分が硬めだった。一方、ラインはPEを使った。このロッドにPEの組み合わせは初めてだった。トゥイッチする度に、小さくバシッという感触が伝わった。当然、糸電話の仕組みで、ルアーも『バシッ』と、小さく鋭い波動を、水中で発しているはず。「もしかしたら、ミノーではなく、このロッドとPEの相性が悪かった可能性がある」と感じた。ダートするミノーがブラウントラウトを寄せても、至近距離に来た途端、この小さな爆発音が、全てを台無しにしていたかもしれない。よく分からない。
その約10分後、岸から3〜4m程度で、ルアーの位置で、魚が反転するギラッという光が見えた。曇天で波が激しいため、サイズまでは分からなかった。こういう見切り方も、このミノーでは初めてだった。
その約30分後、やっと乗った。岸から3〜4m、水深50cmに満たない所でのヒット。やっぱり、疑心暗鬼の乗り方だった。64cmのブラウントラウト (6:27)。やはり、この個体も、お腹が薄っぺらだった。「相当飢えた奴だけが、何とか相手をしてくれている...」と、笑うしかなかった。


その20分後に50cmのブラウントラウト(6:48)。これは、岸から2m。ピックアップ寸前に乗った。このサイズですら、疑心暗鬼のヒットだった。

2時間叩いた後、開始地点に戻った。「このミノーが駄目なら、新しいのを見つけるまで」と考えていた。候補になる奴を1個持ってきた。これで2時間、同じ範囲を叩いた。無反応だった。「少なくとも、今までのミノー以上ではない」と判断できた。
最初のミノーに戻して、さらに、先週に叩けなかった範囲を、ひたすら叩いた。反応したのは40cm前後の2尾だった。1回目は、岸から2〜3mの水深30cm程度まで追尾してきたが、結局、口を使わずに帰っていった。2回目も、水深30cmまで追尾してきて、最後に、食いつくのが見えた。しかし、手元にはコツンッしか伝わらず、フッキングせず、そのまま去って行った。
先週の叩き残しの範囲を、あらかた叩いた11時半。ここで一旦終了。
ついでニナル河口まで湖岸を歩いた。ここで、南岸向けの練習をしてみた。この2ヶ月間の、南岸でのトゥイッチの教訓は「この時期、10gを超えると、ブラウントラウトは、ミノーを餌と見なさずに、喧嘩を売ってくる侵入者と見なす」だった。そこで、気になる5〜10gの、候補になりえそうな奴を1個持って来た。
ダートは「これは凄い!」と思えた。しかし、ダートさせるのに、かなりの力を加える必要があった。これで、ニナル河口の左右合計300m程度を叩いた。反応は2回。1回目。40cm弱が、岸から2m、水深15cmまで、追尾してきて、ミノーに触れることなく帰って行った。2回目。岸から3m、水深20cm程度で、軽い重みが乗った。食う瞬間が丸見えだった。40cm弱のブラウントラウト (13:03)。

最後に、ニナルの南側のワンドで水温を測ると5.1℃。さらに、帰り際に美笛の船着場で測ると5.8℃だった。ニナルの奥の平均3.8℃より、格段に高かった。
これでニナル河口〜フレナイ河口の現時点での状況が、大体、掴めてきた。
この日、最も気になったのが、トゥイッチでのPE使用だった。「ナイロン vs. PE」は、しっかり確認する必要がある。PEの「全く伸びない」というトゥイッチでの弱点は、明らかに「ソリッドティップでは補いきれない」。ナイロンを使えば飛ばない。PEを使えば食わない。そんな印象を受けた。ここに書いたことが本当なのか?も、今の時点では確信できない。今後、しっかりと確かめていきたい。

天気図は日本気象協会(http://www.tenki.jp/guide/chart/)を引用。
月齢:17
気温:日平均9.1℃ (6.2~11.4℃)
水温:3.8℃ (3.7〜3.9℃)
時間:7時間半 (午前5時〜午後1時)
反応:9回
釣果:4尾
この日の目的は、先週に叩けなかったニナル河口〜フレナイ河口の2/3程度の範囲を、全部叩くことだった。
天候は小雨〜雨。南東から強めの波が来ている。「釣れないはずがない」と確信できる条件だった。先行者の要素を排除したいので、早起きして、午前5時過ぎに開始。水温は3.8℃(3.9, 3.7, 3.8, 3.9)。先週より0.3℃上昇したが、未だ、4.0℃以下。このエリアは、まだ早春を引きずっていて、春が来ていない。

先週に引き続き、小さめで軽めのミノーのトゥイッチ。開始4投目で、重みが乗った。ブレイクのショルダーより、かなり手前。岸から3〜4m、水深50cmに満たない所で、いきなりミノーの背後に現れ、その数秒後に乗った。食うことを、かなり躊躇している。しかし何とか丸飲みしてくれた。61cmの、腹が痩せたブラウントラウト (5:18)。


その30分後、岸から6〜7m、水深1m強程度のところで、ミノーの後ろに60cm前後のブラウントラウトがピタリと付いた。しかし、数秒後には反転して去って行った。「マジかっ?」と愕然とした。このミノーのこの反応は、初めてだった。
「やっぱり、このミノーも落ち目か」と感じた。これまでの経験から、「これは凄い!」とビックリしたミノーも、同じエリアで叩き続けると、数年後には全く釣れなくなってしまう。しかし一方で、気になる点があった。
この日は、15年以上前に買った、10gまで投げられる6.1ftのソリッドティップのバスロッドを使った。6.1ftと短く、トゥイッチのロッド操作がしやすい。ただし、ソリッド部分が硬めだった。一方、ラインはPEを使った。このロッドにPEの組み合わせは初めてだった。トゥイッチする度に、小さくバシッという感触が伝わった。当然、糸電話の仕組みで、ルアーも『バシッ』と、小さく鋭い波動を、水中で発しているはず。「もしかしたら、ミノーではなく、このロッドとPEの相性が悪かった可能性がある」と感じた。ダートするミノーがブラウントラウトを寄せても、至近距離に来た途端、この小さな爆発音が、全てを台無しにしていたかもしれない。よく分からない。
その約10分後、岸から3〜4m程度で、ルアーの位置で、魚が反転するギラッという光が見えた。曇天で波が激しいため、サイズまでは分からなかった。こういう見切り方も、このミノーでは初めてだった。
その約30分後、やっと乗った。岸から3〜4m、水深50cmに満たない所でのヒット。やっぱり、疑心暗鬼の乗り方だった。64cmのブラウントラウト (6:27)。やはり、この個体も、お腹が薄っぺらだった。「相当飢えた奴だけが、何とか相手をしてくれている...」と、笑うしかなかった。


その20分後に50cmのブラウントラウト(6:48)。これは、岸から2m。ピックアップ寸前に乗った。このサイズですら、疑心暗鬼のヒットだった。

2時間叩いた後、開始地点に戻った。「このミノーが駄目なら、新しいのを見つけるまで」と考えていた。候補になる奴を1個持ってきた。これで2時間、同じ範囲を叩いた。無反応だった。「少なくとも、今までのミノー以上ではない」と判断できた。
最初のミノーに戻して、さらに、先週に叩けなかった範囲を、ひたすら叩いた。反応したのは40cm前後の2尾だった。1回目は、岸から2〜3mの水深30cm程度まで追尾してきたが、結局、口を使わずに帰っていった。2回目も、水深30cmまで追尾してきて、最後に、食いつくのが見えた。しかし、手元にはコツンッしか伝わらず、フッキングせず、そのまま去って行った。
先週の叩き残しの範囲を、あらかた叩いた11時半。ここで一旦終了。
ついでニナル河口まで湖岸を歩いた。ここで、南岸向けの練習をしてみた。この2ヶ月間の、南岸でのトゥイッチの教訓は「この時期、10gを超えると、ブラウントラウトは、ミノーを餌と見なさずに、喧嘩を売ってくる侵入者と見なす」だった。そこで、気になる5〜10gの、候補になりえそうな奴を1個持って来た。
ダートは「これは凄い!」と思えた。しかし、ダートさせるのに、かなりの力を加える必要があった。これで、ニナル河口の左右合計300m程度を叩いた。反応は2回。1回目。40cm弱が、岸から2m、水深15cmまで、追尾してきて、ミノーに触れることなく帰って行った。2回目。岸から3m、水深20cm程度で、軽い重みが乗った。食う瞬間が丸見えだった。40cm弱のブラウントラウト (13:03)。

最後に、ニナルの南側のワンドで水温を測ると5.1℃。さらに、帰り際に美笛の船着場で測ると5.8℃だった。ニナルの奥の平均3.8℃より、格段に高かった。
これでニナル河口〜フレナイ河口の現時点での状況が、大体、掴めてきた。
この日、最も気になったのが、トゥイッチでのPE使用だった。「ナイロン vs. PE」は、しっかり確認する必要がある。PEの「全く伸びない」というトゥイッチでの弱点は、明らかに「ソリッドティップでは補いきれない」。ナイロンを使えば飛ばない。PEを使えば食わない。そんな印象を受けた。ここに書いたことが本当なのか?も、今の時点では確信できない。今後、しっかりと確かめていきたい。

天気図は日本気象協会(http://www.tenki.jp/guide/chart/)を引用。