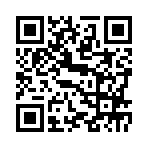2016年10月30日
支笏湖2016年10月29日
方法:岸からの釣り
月齢:28
気温:日平均 2.1℃ (-0.6~5.0℃)
水温:10.3℃ (10.1~10.5℃)
時間:5時間 (午前9時〜15時)
反応:1回
釣果:1尾
この一週間、札幌は穏やかな天気だった。寒波が来たわけでもなく、雪も降らなかった。そこで、先週の水温11.6℃が10℃を切るとは思えず「今日も無反応の確認か...」という気分で釣行。しかし、水温は意外と下がっていた。平均で10.3℃(10.1, 10.5, 10.4)。この推移から、あと数日もあれば10℃を切ってシーズンに入りそうな期待がある。波はこの日も「釣れないはずがない」と思える状態だった。10℃に達していないが「気の早い奴が1尾や2尾いないだろうか?」と淡い期待を抱いた。

午前9時に1つめのエリアで開始した。1時間かけて、初めて使うミノーをリアクション狙いで激しめに操作してみた。開始して40分後に軽い重みが乗った。30cm程度のブラウントラウト (9:42)。先週同様、岸から数m、水深50cm程度の場所で食ってきた。相変わらず、的を外した釣り方になっているようだった。

さらに、同じエリアを1時間だけ、食わせを意識してルアーを繊細に操作してみた。しかし無反応だった。岸際にブラウントラウトが差していれば、フッキングまで至らなくても、ショートバイトや追尾は必ずあると自信をもてる方法だった。「まだシャローに来ていない」という判断が妥当のように感じた。
午前11時にこのエリアに見切りをつけ、次のエリアに移動して正午 (12:00) に再開。3時間丹念に1km程度の範囲を攻めたが、完全に無反応。追尾もショートバイトも無かった。基本的に先週と全く同じ1日だった。
なお、美笛のゲートは11月7日(月) 午前11時に閉鎖されるとの掲示が出ていた。


気圧配置図は日本気象協会(http://www.tenki.jp/guide/chart/)を引用。FLR_08_CL_GR。
月齢:28
気温:日平均 2.1℃ (-0.6~5.0℃)
水温:10.3℃ (10.1~10.5℃)
時間:5時間 (午前9時〜15時)
反応:1回
釣果:1尾
この一週間、札幌は穏やかな天気だった。寒波が来たわけでもなく、雪も降らなかった。そこで、先週の水温11.6℃が10℃を切るとは思えず「今日も無反応の確認か...」という気分で釣行。しかし、水温は意外と下がっていた。平均で10.3℃(10.1, 10.5, 10.4)。この推移から、あと数日もあれば10℃を切ってシーズンに入りそうな期待がある。波はこの日も「釣れないはずがない」と思える状態だった。10℃に達していないが「気の早い奴が1尾や2尾いないだろうか?」と淡い期待を抱いた。

午前9時に1つめのエリアで開始した。1時間かけて、初めて使うミノーをリアクション狙いで激しめに操作してみた。開始して40分後に軽い重みが乗った。30cm程度のブラウントラウト (9:42)。先週同様、岸から数m、水深50cm程度の場所で食ってきた。相変わらず、的を外した釣り方になっているようだった。

さらに、同じエリアを1時間だけ、食わせを意識してルアーを繊細に操作してみた。しかし無反応だった。岸際にブラウントラウトが差していれば、フッキングまで至らなくても、ショートバイトや追尾は必ずあると自信をもてる方法だった。「まだシャローに来ていない」という判断が妥当のように感じた。
午前11時にこのエリアに見切りをつけ、次のエリアに移動して正午 (12:00) に再開。3時間丹念に1km程度の範囲を攻めたが、完全に無反応。追尾もショートバイトも無かった。基本的に先週と全く同じ1日だった。
なお、美笛のゲートは11月7日(月) 午前11時に閉鎖されるとの掲示が出ていた。


気圧配置図は日本気象協会(http://www.tenki.jp/guide/chart/)を引用。FLR_08_CL_GR。
2016年10月24日
支笏湖2016年10月23日
方法:岸からの釣り
月齢:22
気温:日平均 4.0℃ (0.5~7.2℃)
水温:11.6℃ (10.7~12.6℃)
時間:4時間半 (午前9時〜14時半)
反応:2回
釣果:2尾
下見を目的に釣行。4ヶ月半ぶりの支笏湖だった。札幌では3日前の10/20(木)に、まとまった量の初雪が降った。支笏湖のライブカメラ
http://www.sizenken.biodic.go.jp/
で翌朝の画像を見ると、湖岸に雪は見えないが砂浜全体が濡れている。加えて、背後の山の雪が増えている。そこで、少量ではあっても湖に雪が降った可能性がある (写真は10/21(金)午前6時の写真を引用)。

天気は曇り時々晴れ。水温は平均で11.6℃(11.5, 12.0, 12.6, 11.4, 10.7, 11.6, 11.7)。ハイシーズンに入る10℃まで、あと1.6℃。もう1回雪が降ればシーズンに入りそうな感じだった。今年は例年に比べて水位が30cm程度高い。波は、開始時は風裏で、穏やかだった。2時間後から北風が吹き、波だけを見たら、「釣れないはずがない」と確信できる状況が続いた。

この日の課題は釣り方だった。この数年で痛感したことがある。晩秋のハイシーズンは、「食わせ」だけを意識し、水面から1m以内の浅さの中で、出来る限り繊細に、ネチネチした攻め方をしていると、なんとか釣果が得られる。そんな感じだった。しかし、水温10℃以上のシーズン前と、10℃を切った直後のシーズン初期は、この攻め方が全く効かない。無視とショートバイトばかりだった。一方、フライの人達は、釣行の度、1〜数尾の釣果を上げている。
打開策を探す必要があると感じていた。ただし、虫系のルアーは退屈で使う気になれない。この日は、リアクションの要素が入りそうなルアーを数個買って持ってきた。そのうち、無難そうなのを1個選び、手返し良く、エリア全体を流すことを試みた。
午前9時に1つめのエリアで1km程度の範囲をチェックした。1時間半経ったところで、やっと、軽い重みが乗った。30cmに満たないブラウントラウト (10:33)。

その数投後に30cm程度のブラウントラウト (10:40)。

2尾とも、ブレイクのショルダーが岸から7〜8m程度の場所で、ヒットしたのはさらに手前。岸から数m、水深30〜50cm程度のところだった。ルアーを食うのをためらい続け、しかし気になりつつ、最後の最後にやっと口を使った感じだった。この小さなサイズが相手なのに、明らかな大苦戦。「このルアーは完全な不正解ではない。しかし完全に、正解ではない」という印象を受けた。もしかしたら、もう少し良いサイズも岸際に居て、しかし無視されただけ...という可能性も十分にある。
念のため、ネチネチした攻め方で1時間程度、この場所中心に300m程度の範囲を攻めてみた。完全に無反応だった。「去年同様、この時期、この攻め方は完全な不正解」と確認できた。そう強がって、自分を慰めるしかなかった。今年も、新しい発見の手掛かりがない。
ルアーを戻し、2つめのエリアに移動し、12時半に再開。1km程度の範囲に2時間かけたが、完全に無反応。追尾すらなかった。さらに1km以上を残しているが「馬鹿らしい。シーズン前のこの時期に、これ以上やっても、体力と時間の無駄」と感じ、午後2時半に終了。
追記: ヒグマのような糞を2つ見ました。重さで1kgから1.5kg程度。私は、ヒグマの糞らしきものを見ること自体が初めてです。経験のある方がいらして、もし『間違っている」と判断されたら、指摘してもらえると助かります。
1つは、美笛からニナル方向へ向かう林道です。ゲートから60〜70mの林道の真ん中。


もう1つは、ニナル河口の南側のワンドです。ここに、林道に登る細い坂道があります。この道の入り口辺りにありました。


もしこうした糞がヒグマなら、今年は、まだ10月なのに、湖岸まで自由に行動しているようです。この8〜9年、晩秋のお昼の時間帯にはこのエリアに通い続けていますが、こうした経験は初めてでした。例年だと、この時期は、たまにヒグマが吠える声を聞きます。しかし林道の山側で、100mや200mは離れたところから聞こえます。林道を超えて湖岸側に来ることは、根雪が出来始める頃の、ほんの一時期だけでした。
この周辺で獣臭がすることを書き込まれている方もいます。
http://blogs.yahoo.co.jp/sicobakasikobaka
今年の西岸は、ヒグマが湖岸まで行動範囲を広げていることを前提に釣行する必要があるかもしれません。

気圧配置図は日本気象協会(http://www.tenki.jp/guide/chart/)を引用。BRN_09_AY_GR。
月齢:22
気温:日平均 4.0℃ (0.5~7.2℃)
水温:11.6℃ (10.7~12.6℃)
時間:4時間半 (午前9時〜14時半)
反応:2回
釣果:2尾
下見を目的に釣行。4ヶ月半ぶりの支笏湖だった。札幌では3日前の10/20(木)に、まとまった量の初雪が降った。支笏湖のライブカメラ
http://www.sizenken.biodic.go.jp/
で翌朝の画像を見ると、湖岸に雪は見えないが砂浜全体が濡れている。加えて、背後の山の雪が増えている。そこで、少量ではあっても湖に雪が降った可能性がある (写真は10/21(金)午前6時の写真を引用)。

天気は曇り時々晴れ。水温は平均で11.6℃(11.5, 12.0, 12.6, 11.4, 10.7, 11.6, 11.7)。ハイシーズンに入る10℃まで、あと1.6℃。もう1回雪が降ればシーズンに入りそうな感じだった。今年は例年に比べて水位が30cm程度高い。波は、開始時は風裏で、穏やかだった。2時間後から北風が吹き、波だけを見たら、「釣れないはずがない」と確信できる状況が続いた。

この日の課題は釣り方だった。この数年で痛感したことがある。晩秋のハイシーズンは、「食わせ」だけを意識し、水面から1m以内の浅さの中で、出来る限り繊細に、ネチネチした攻め方をしていると、なんとか釣果が得られる。そんな感じだった。しかし、水温10℃以上のシーズン前と、10℃を切った直後のシーズン初期は、この攻め方が全く効かない。無視とショートバイトばかりだった。一方、フライの人達は、釣行の度、1〜数尾の釣果を上げている。
打開策を探す必要があると感じていた。ただし、虫系のルアーは退屈で使う気になれない。この日は、リアクションの要素が入りそうなルアーを数個買って持ってきた。そのうち、無難そうなのを1個選び、手返し良く、エリア全体を流すことを試みた。
午前9時に1つめのエリアで1km程度の範囲をチェックした。1時間半経ったところで、やっと、軽い重みが乗った。30cmに満たないブラウントラウト (10:33)。

その数投後に30cm程度のブラウントラウト (10:40)。

2尾とも、ブレイクのショルダーが岸から7〜8m程度の場所で、ヒットしたのはさらに手前。岸から数m、水深30〜50cm程度のところだった。ルアーを食うのをためらい続け、しかし気になりつつ、最後の最後にやっと口を使った感じだった。この小さなサイズが相手なのに、明らかな大苦戦。「このルアーは完全な不正解ではない。しかし完全に、正解ではない」という印象を受けた。もしかしたら、もう少し良いサイズも岸際に居て、しかし無視されただけ...という可能性も十分にある。
念のため、ネチネチした攻め方で1時間程度、この場所中心に300m程度の範囲を攻めてみた。完全に無反応だった。「去年同様、この時期、この攻め方は完全な不正解」と確認できた。そう強がって、自分を慰めるしかなかった。今年も、新しい発見の手掛かりがない。
ルアーを戻し、2つめのエリアに移動し、12時半に再開。1km程度の範囲に2時間かけたが、完全に無反応。追尾すらなかった。さらに1km以上を残しているが「馬鹿らしい。シーズン前のこの時期に、これ以上やっても、体力と時間の無駄」と感じ、午後2時半に終了。
追記: ヒグマのような糞を2つ見ました。重さで1kgから1.5kg程度。私は、ヒグマの糞らしきものを見ること自体が初めてです。経験のある方がいらして、もし『間違っている」と判断されたら、指摘してもらえると助かります。
1つは、美笛からニナル方向へ向かう林道です。ゲートから60〜70mの林道の真ん中。


もう1つは、ニナル河口の南側のワンドです。ここに、林道に登る細い坂道があります。この道の入り口辺りにありました。


もしこうした糞がヒグマなら、今年は、まだ10月なのに、湖岸まで自由に行動しているようです。この8〜9年、晩秋のお昼の時間帯にはこのエリアに通い続けていますが、こうした経験は初めてでした。例年だと、この時期は、たまにヒグマが吠える声を聞きます。しかし林道の山側で、100mや200mは離れたところから聞こえます。林道を超えて湖岸側に来ることは、根雪が出来始める頃の、ほんの一時期だけでした。
この周辺で獣臭がすることを書き込まれている方もいます。
http://blogs.yahoo.co.jp/sicobakasikobaka
今年の西岸は、ヒグマが湖岸まで行動範囲を広げていることを前提に釣行する必要があるかもしれません。

気圧配置図は日本気象協会(http://www.tenki.jp/guide/chart/)を引用。BRN_09_AY_GR。